SSBJ開示基準と補足文書の役割 ~実務を支える具体例とその意義~
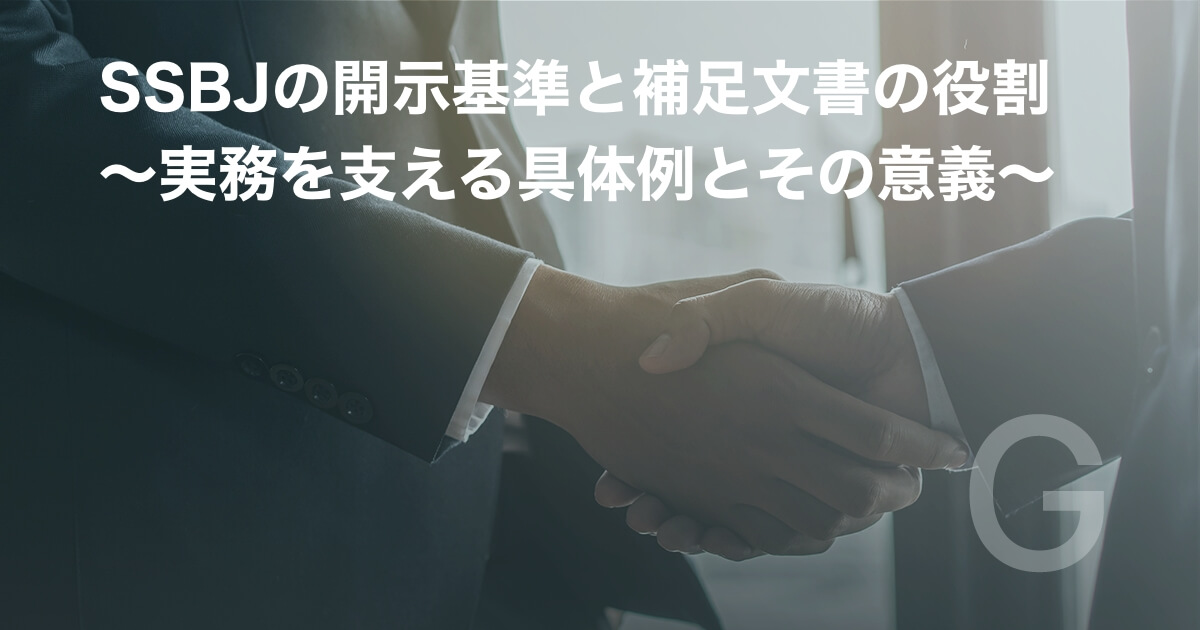
目次
企業のサステナビリティ情報の制度開示が求められる時代にあって、日本におけるその中核を担うのがサステナビリティ基準委員会(SSBJ)です。SSBJは国際基準との整合性を保ちつつ、日本の法制度や実務に即した開示基準を策定し、企業が適切な制度開示を行えるよう支援しています。その基準運用を補完するために整備されている「補足文書」は、実務上の理解と対応を深める重要な手がかりとなっています。本記事では、SSBJの開示基準の構成と、補足文書の具体的な内容、そして制度開示における役割を整理します。
SSBJ開示基準の構成と制度開示への対応
SSBJは2025年3月、日本企業における制度開示の共通基盤となる3つのサステナビリティ開示基準を公表しています。
- 「ユニバーサル基準」:全体の枠組みと適用に関する基本事項
- 「テーマ別基準 第1号」:戦略・ガバナンス・リスク管理に関する一般的な開示要件
- 「テーマ別基準 第2号」:気候関連リスクや機会に関する具体的な開示要求
これらの基準は、ISSB(国際サステナビリティ基準審議会)が策定したIFRS S1・S2号に準拠し、グローバルな整合性を維持しつつ、日本企業が現実的かつ適切に制度開示を実行できるよう設計されています。企業はこれらの基準に基づき、サステナビリティ関連情報を、法令や市場要請に即した形で開示することが求められます。

図1:SSBJ開示基準の構成イメージ:(出典:金融庁 「SSBJ基準の概要」)
補足文書の実務的役割と具体例
SSBJは、上記3つの開示基準への対応を実務レベルで支援するために、「補足文書」と呼ばれる参考資料を整備・公表しています。補足文書は開示基準の一部ではなく、参照は任意とされていますが、基準内容の理解を補い、実務での適用を円滑にする役割を担っています。
2025年6月には、ISSBが公表した教育的資料「IFRS S2号の適用にあたっての温室効果ガス(GHG)排出の開示要求」が補足文書として追加されました。この文書では、スコープ1・2・3に分類されるGHG排出量の定義、測定方法、報告の留意点などが具体的に示されており、企業の開示情報の質を担保するうえで極めて有用な資料です。
他にも、「SASBスタンダードの活用」 「財務的影響の評価」 「リスク及び機会、重要性」などをテーマとした8件の教育的資料が翻訳・整理され、補足文書として提供されています。これらは、制度開示に必要な実務知識の獲得を目指す企業にとって、具体的な判断の指針となります。
補足文書と制度開示の未来
IFRS/SSBJが求める情報開示は単なるコンプライアンス対応にとどまらず、企業価値やリスク管理に関する情報を市場に的確に伝える手段でもあります。SSBJの補足文書を活用することで、企業は形式面だけでなく内容面においても充実した開示が可能となり、投資家やステークホルダーとの信頼関係の構築にもつながります。
補足文書は、基準そのものを変更・補完するものではないため、参照しなくともSSBJ基準に準拠していると見なされますが、基準の解釈や実装における理解を深め、実務への落とし込みをスムーズにする重要な資料群です。今後、ISSBが進めている生物多様性や人的資本の開示プロジェクトに応じて、さらなる補足資料の追加も見込まれます。企業はこれらの更新動向に継続的に注目し、柔軟かつ的確な情報開示体制の構築が求められます。
まとめ
SSBJが策定する開示基準は、日本企業が国際基準と整合性を保ちながら、的確な制度開示を行うための基盤です。そして補足文書は、その制度開示を実務に落とし込むうえでの実践的なツールとして機能します。具体例を交えた補足文書の活用は、企業におけるサステナビリティ活動の質を高め、制度開示を円滑に進めるうえで重要な情報です。今後も補足文書の拡充と企業における適切な運用が、企業にとって不可欠な要素となっていくことは間違いありません。企業は補足文書を積極的に活用し、持続可能な情報開示の質を高めていくことが期待されます。
出典
SSBJ サステナビリティ基準委員会がサステナビリティ開示基準を公表|サステナビリティ基準委員会
SSBJ 補足文書|サステナビリティ基準委員会
SSBJ ユニバーサル基準
SSBJ テーマ別基準 第1号
SSBJ テーマ別基準 第2号
金融庁 SSBJ基準の概要
IFRS ISSB to commence research projects about risks and opportunities related to nature and human capital
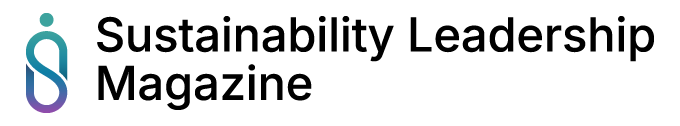


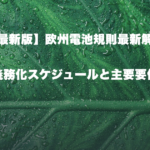
とは-―-製品のGHG見える化から企業全体の削減へ-150x150.png)
