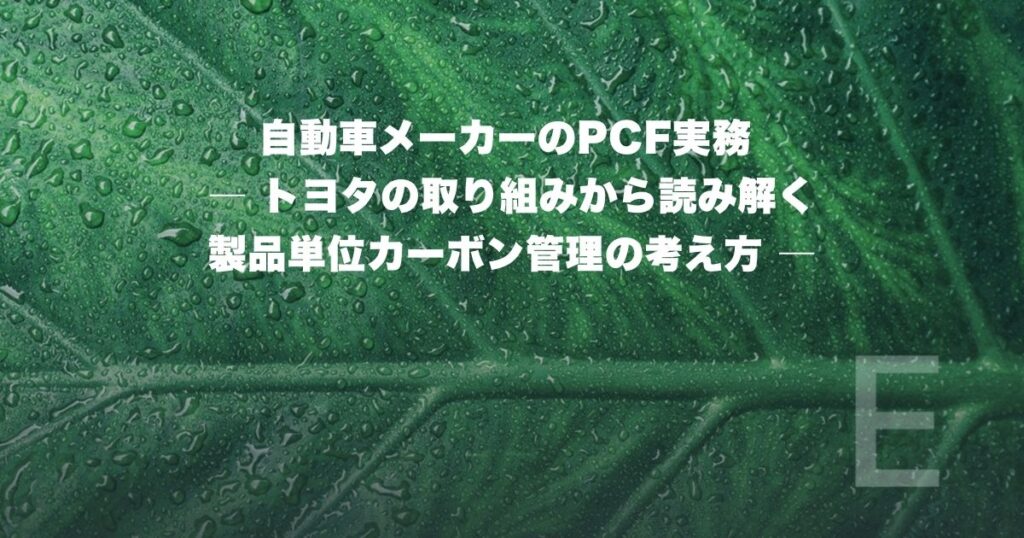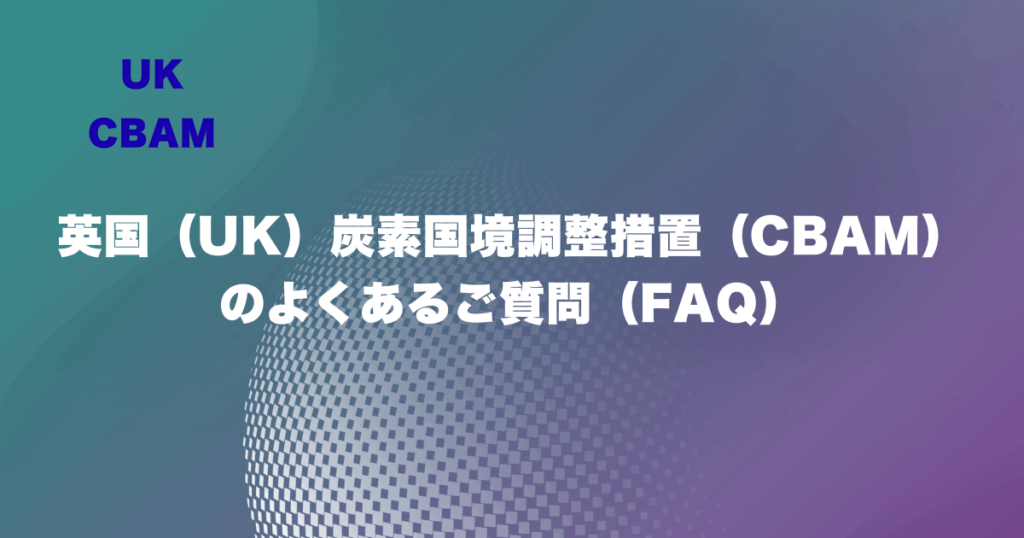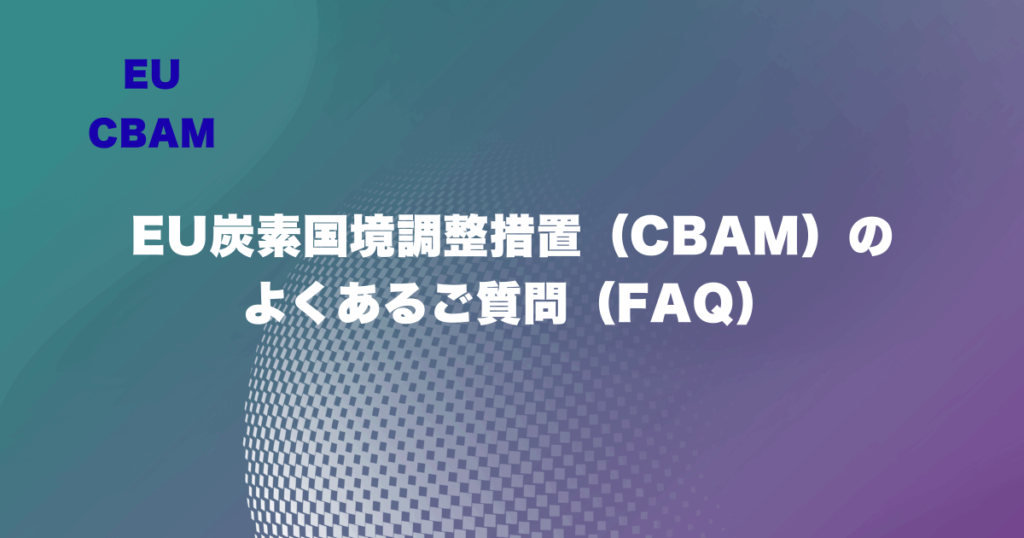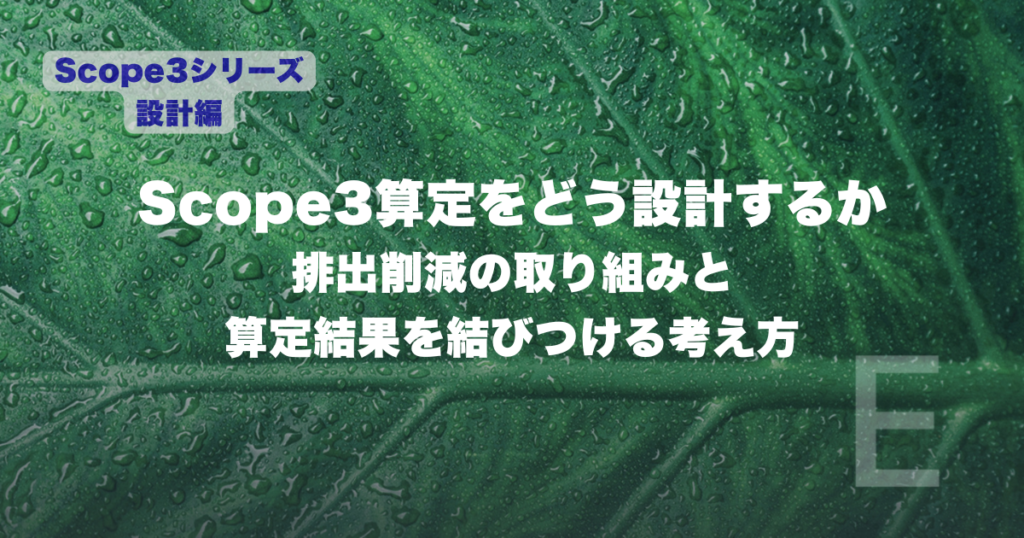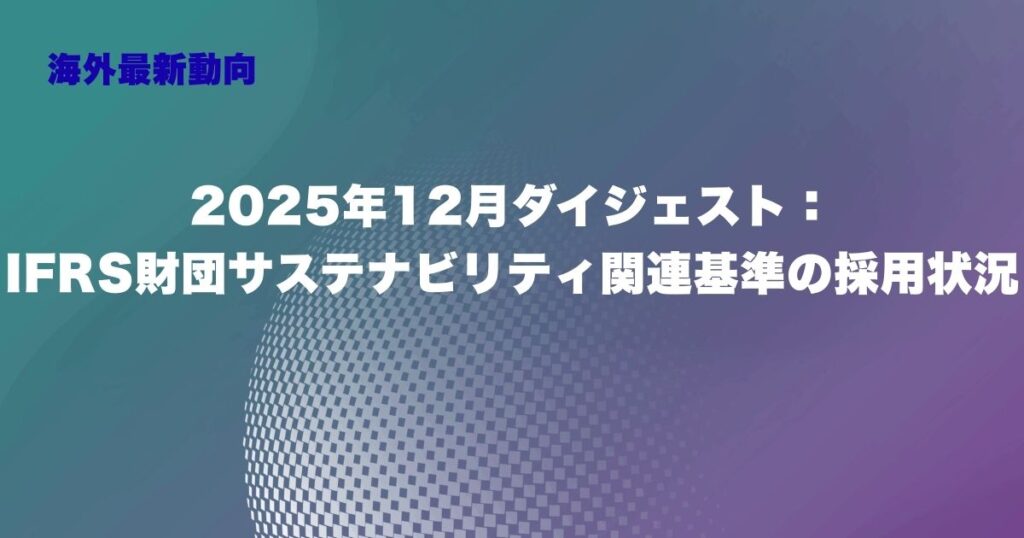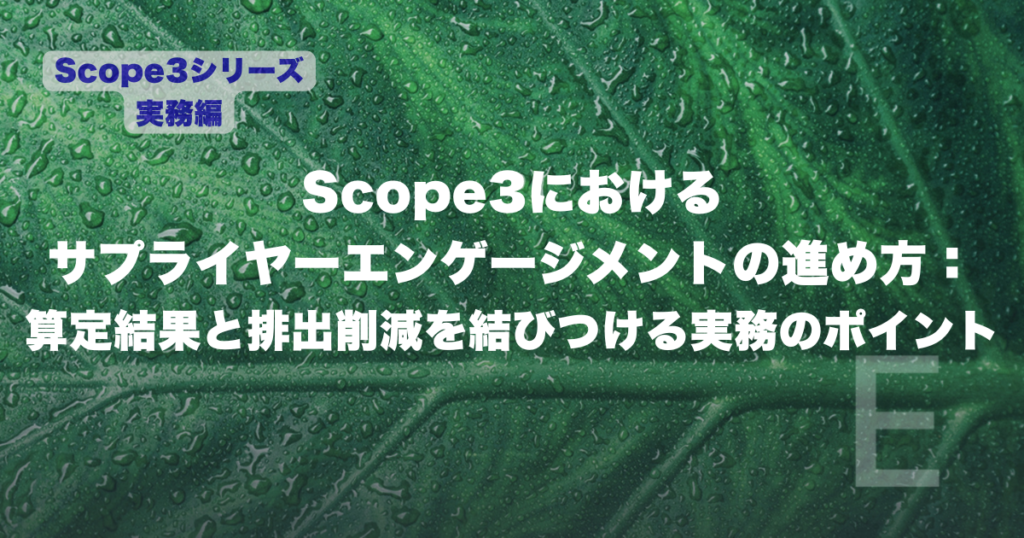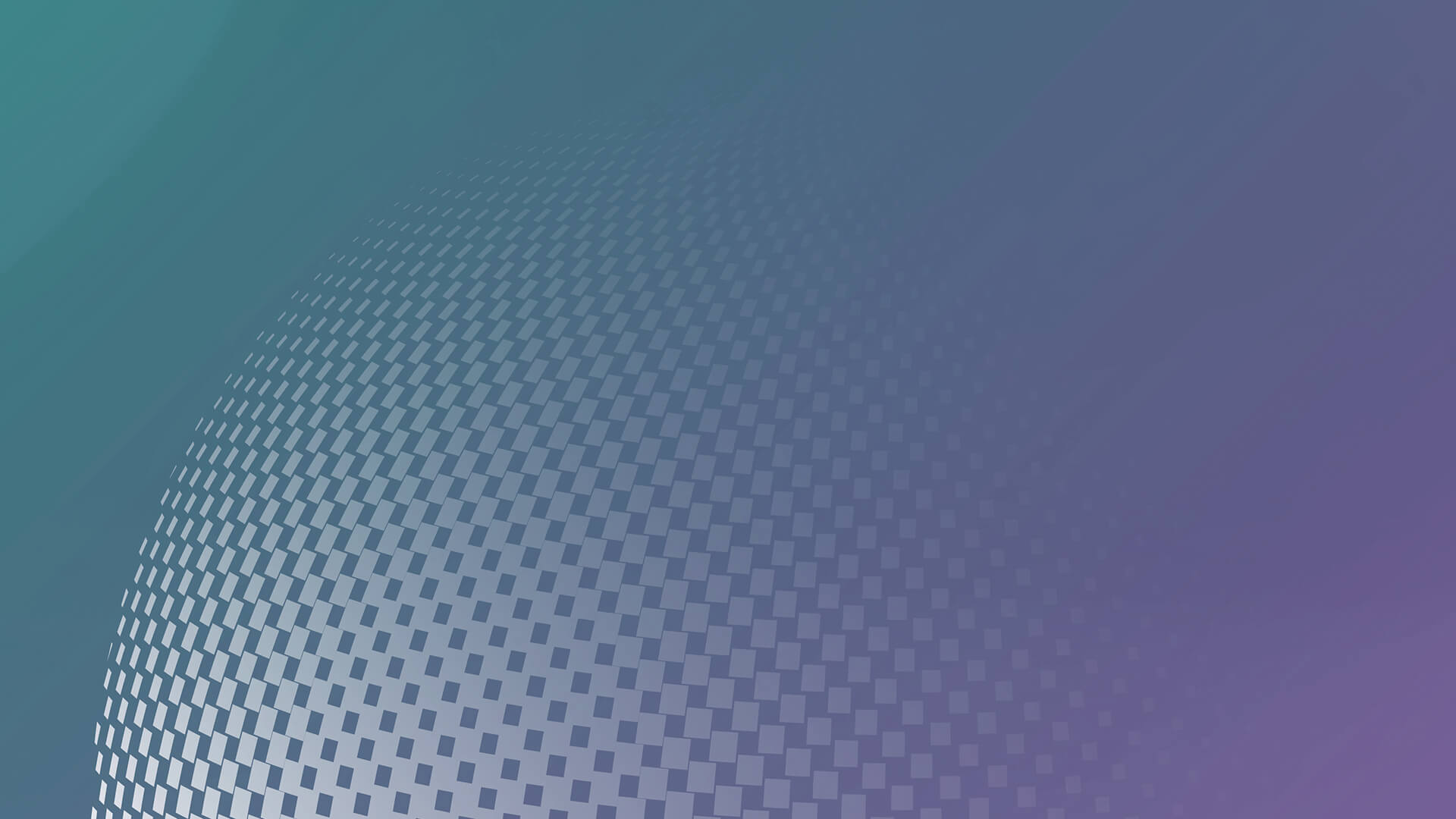
サステナビリティ経営で
企業価値を高める
環境・社会課題の解決と企業成長の両立に向けた
実践的な知見とソリューションをお届けします
最新記事
最新動向
海外
英国(UK)炭素国境調整措置(CBAM)の二次法(Secondary legislation)のパブリックコメント開始
英国政府は炭素国境調整措置のCBAM二次法令案を公表しパブリックコメントを開始 英国政府は、炭素国境…
最新動向
海外
EU、世界初の恒久的炭素除去の自主認証基準を策定 DACCS・BioCCSなど対象に市場創出へ
欧州委員会は、大気中からCO₂を恒久的に除去する活動を認証するための初の自主基準を採択しました。これ…
企業規制(日本) すべて見る
企業規制(日本)SSBJ
SSBJ(サステナビリティ開示基準)とは?制度の全体像と企業対応を体系整理
本記事は、SSBJに関する個別解説や対応手順を網羅することを目的としたものではありません。Susta…
その他企業規制(日本)企業規制(海外)CSRDSSBJScope1,2,3
Scope3算定はなぜ難しいのか 有価証券報告書・SSBJ開示で説明が難しくなる理由
本記事は、Scope3/サプライチェーン排出量を体系的に整理するシリーズの【課題編|なぜScope3…
企業規制(日本)CFPSSBJScope1,2,3サステナ経営第三者保証
金融審議会WG報告で何が決まったのか SSBJ開示と第三者保証の最新整理(2026年1月版)
企業のサステナビリティ情報開示を巡る議論は、2025年以降、制度設計の具体化が急速に進んでいます。 …
企業規制(海外) すべて見る
企業規制(海外)製品規制(日本)製品規制(海外)CFPグローバル基準欧州電池規則
電池業界のカーボンフットプリント(CFP/PCF)とは? 欧州電池規則・バッテリーパスポートを踏まえた実務整理
電池業界では、製品・サプライチェーン単位で温室効果ガス(GHG)排出量を捉える枠組みとして、カーボン…
その他企業規制(日本)企業規制(海外)CSRDSSBJScope1,2,3
Scope3算定はなぜ難しいのか 有価証券報告書・SSBJ開示で説明が難しくなる理由
本記事は、Scope3/サプライチェーン排出量を体系的に整理するシリーズの【課題編|なぜScope3…
企業規制(日本)企業規制(海外)CSRDSSBJサステナ経営
SSBJ・CSRD・IFRS S1/S2をどう読み解くべきか? 企業価値評価に使われるサステナビリティ開示の共通構造
現在のサステナビリティ開示制度は、IFRS S1/S2をグローバル標準(企業価値評価の共通言語)とし…
製品規制(日本) すべて見る
企業規制(海外)製品規制(日本)製品規制(海外)CFPグローバル基準欧州電池規則
電池業界のカーボンフットプリント(CFP/PCF)とは? 欧州電池規則・バッテリーパスポートを踏まえた実務整理
電池業界では、製品・サプライチェーン単位で温室効果ガス(GHG)排出量を捉える枠組みとして、カーボン…
製品規制(日本)製品規制(海外)CFP
カーボンフットプリント(CFP)とは?全体像・関連記事の読み方を整理
CFP(カーボンフットプリント)について調べ始めると、「定義」「算定方法」「Scope3との違い」「…
製品規制(日本)製品規制(海外)CFPDPPESPR
自動車メーカーのPCF実務 ― トヨタの取り組みから読み解く製品単位カーボン管理の考え方 ―
自動車産業では近年、電動化の進展と同時に、環境負荷の評価軸が「企業全体」から「製品単位」へと移行しつ…
製品規制(海外) すべて見る
最新動向製品規制(海外)CBAM国内海外
EU炭素国境調整措置(CBAM)のよくあるご質問(FAQ)
Booost株式会社が主催するセミナー※等を通じて多くの方からいただいたご質問について、2025年1…
企業規制(海外)製品規制(日本)製品規制(海外)CFPグローバル基準欧州電池規則
電池業界のカーボンフットプリント(CFP/PCF)とは? 欧州電池規則・バッテリーパスポートを踏まえた実務整理
電池業界では、製品・サプライチェーン単位で温室効果ガス(GHG)排出量を捉える枠組みとして、カーボン…
ガバナンス すべて見る
その他会員限定コンテンツScope1,2,3サステナ経営
Scope3算定をどう設計するか~排出削減の取り組みと算定結果を結びつける考え方
本記事は、Scope3/サプライチェーン排出量を体系的に整理するシリーズの【設計編|算定結果をどう使…
企業規制(日本)CFPSSBJScope1,2,3サステナ経営第三者保証
金融審議会WG報告で何が決まったのか SSBJ開示と第三者保証の最新整理(2026年1月版)
企業のサステナビリティ情報開示を巡る議論は、2025年以降、制度設計の具体化が急速に進んでいます。 …
企業規制(日本)企業規制(海外)CSRDSSBJサステナ経営
SSBJ・CSRD・IFRS S1/S2をどう読み解くべきか? 企業価値評価に使われるサステナビリティ開示の共通構造
現在のサステナビリティ開示制度は、IFRS S1/S2をグローバル標準(企業価値評価の共通言語)とし…
その他 すべて見る
企業規制(海外)製品規制(日本)製品規制(海外)CFPグローバル基準欧州電池規則
電池業界のカーボンフットプリント(CFP/PCF)とは? 欧州電池規則・バッテリーパスポートを踏まえた実務整理
電池業界では、製品・サプライチェーン単位で温室効果ガス(GHG)排出量を捉える枠組みとして、カーボン…
最新動向グローバル基準海外
2025年12月ダイジェスト:IFRS財団サステナビリティ関連基準の採用状況
IFRS財団は、サステナビリティ関連基準およびフレームワークを、公的に利用可能な企業文書において参照…
その他会員限定コンテンツScope1,2,3
Scope3におけるサプライヤーエンゲージメントの進め方:算定結果と排出削減を結びつける実務のポイント
本記事は、Scope3/サプライチェーン排出量を体系的に整理するシリーズの【実務編|サプライヤーエン…
会員限定コンテンツ すべて見る
その他会員限定コンテンツScope1,2,3
Scope3におけるサプライヤーエンゲージメントの進め方:算定結果と排出削減を結びつける実務のポイント
本記事は、Scope3/サプライチェーン排出量を体系的に整理するシリーズの【実務編|サプライヤーエン…
その他会員限定コンテンツScope1,2,3サステナ経営
Scope3算定をどう設計するか~排出削減の取り組みと算定結果を結びつける考え方
本記事は、Scope3/サプライチェーン排出量を体系的に整理するシリーズの【設計編|算定結果をどう使…
ガバナンス企業規制(日本)会員限定コンテンツ最新動向SSBJイベントレポートサステナ経営国内
【ウェビナーアーカイブ】先行企業に学ぶ、レギュレーション対応事例 :「制度対応×企業価値向上」を同時に実現する実践的アプローチ
こちらは、2025年12月9日に開催したBooost ウェビナーのアーカイブです。 開催概要 ◆タイ…
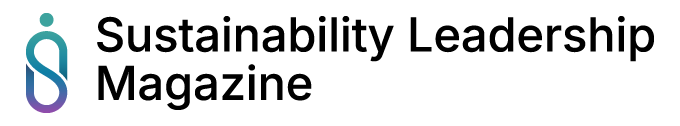

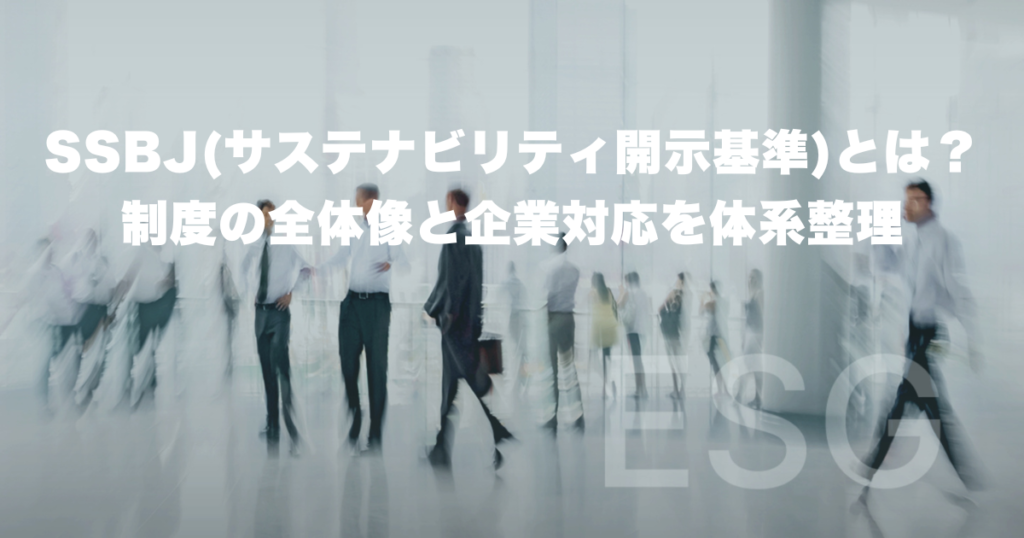
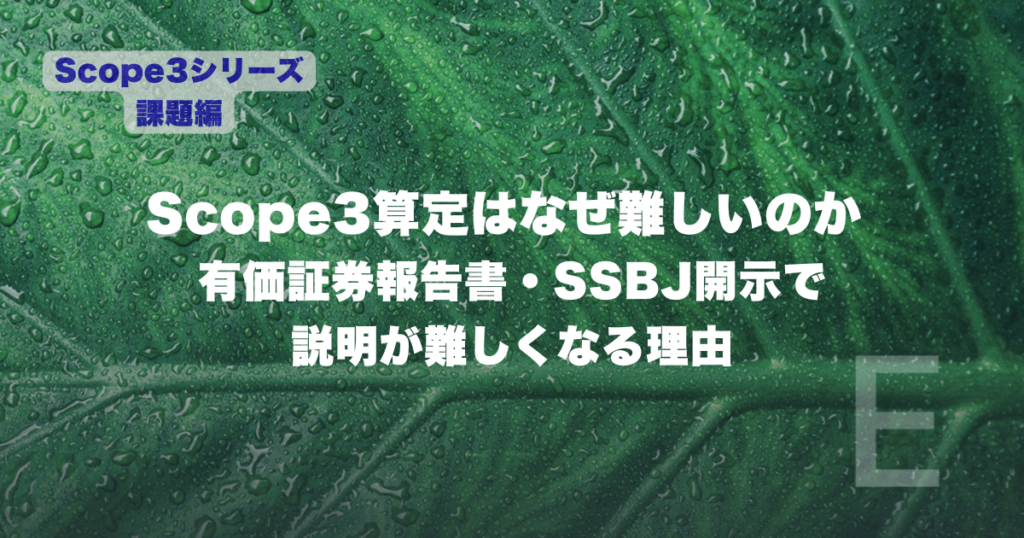
-1024x538.png)
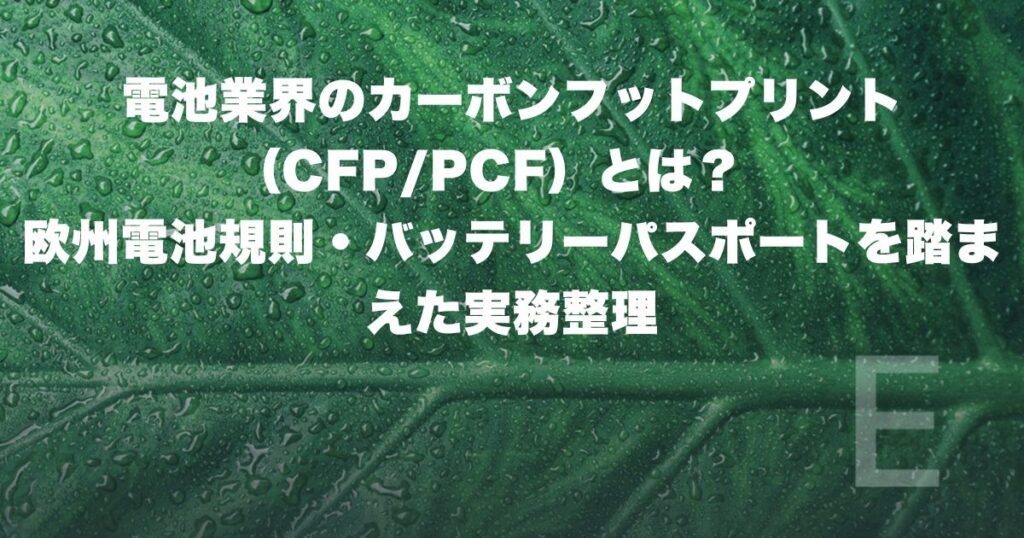
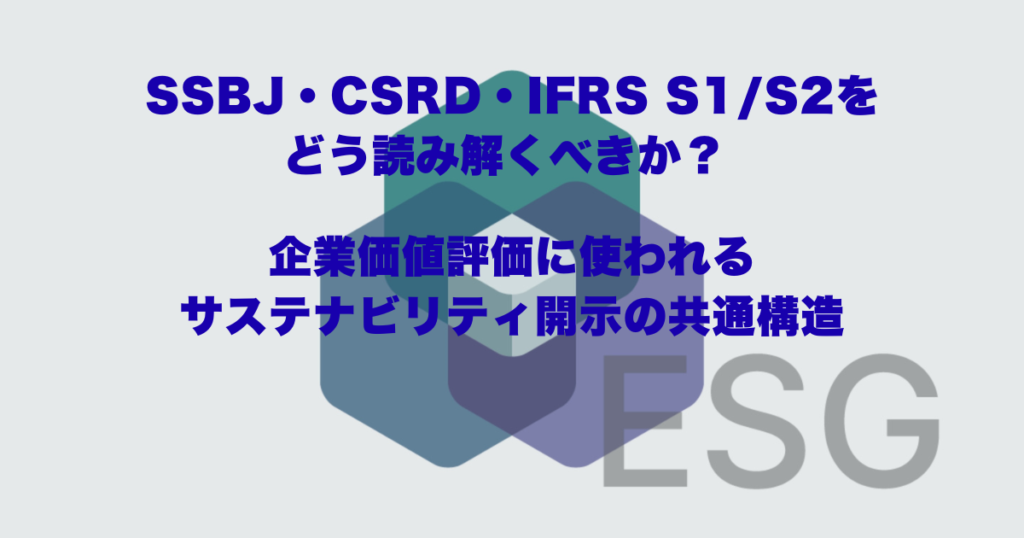
とは?全体像・関連記事の読み方を整理-1024x538.png)