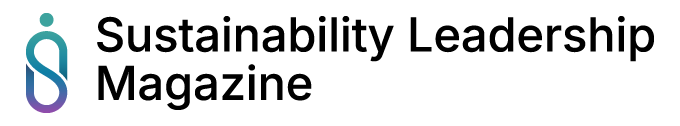DPP:製品の透明性を担保するデジタル製品パスポートとは?
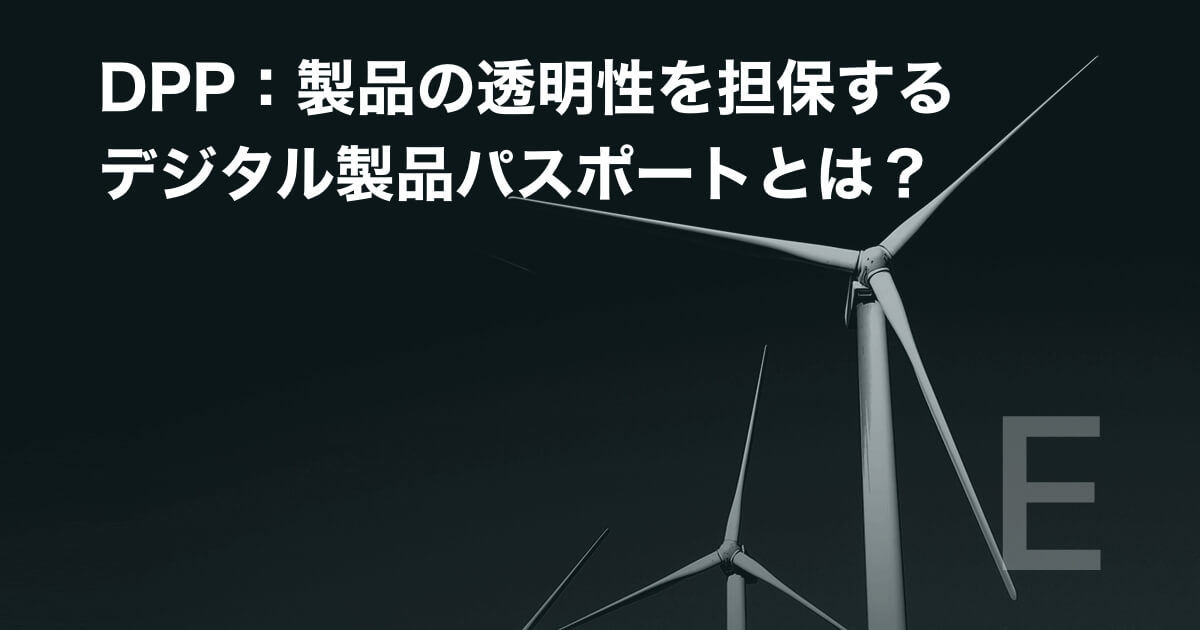
目次
前回の記事で紹介したEUのエコデザイン規則(ESPR)は、持続可能な製品づくりを推進する基盤です。その鍵となるのが、製品のライフサイクルを透明化するデジタル製品パスポート(DPP)です。
製品に貼られたQRコードをスマホで読み取ることで、素材の産地、環境負荷、リサイクル方法等が一目でわかる環境を目指しています。本記事では、DPPの制度概要や導入スケジュールを整理するとともに、日本企業にとっての意義や対応のメリットについて解説します。
デジタル製品パスポート(DPP)とは?
DPPは、ESPRに基づく電子情報システムで、製品ごとの構成、環境影響、ライフサイクル情報をQRコードやRFID(Radio Frequency Identification:無線通信によって情報を読み書きできる電子タグ)を通じて関係者(消費者、企業、規制当局)に提供します。その目的は、製品の持続可能性を“見える化”し、透明で信頼性の高い情報共有を実現することです。
以下のような活用が期待されます:
- 消費者:環境性能や修理のしやすさを比較し、より良い購買判断が可能に。
- 企業:サプライチェーンを最適化し、ESG評価を向上。
- 規制当局:輸入時の税関チェックを効率化。
DPP導入スケジュールと委任法との関係
DPPは、ESPRの優先製品カテゴリーごとに、今後の委任法(Delegated Act)によって段階的に導入される予定です。これとは別に、バッテリー分野ではBattery Regulation(Regulation (EU) 2023/1542)に基づくバッテリーパスポートが2027年2月より義務化され、DPPの先行モデルと見なされています。
衣料・アパレル分野でも、2027年以降にDPPの導入が予定されており、さらに家具やタイヤなどの製品群についても、今後の委任法によって対象範囲が順次拡大される見込みです。
EU市場に最終製品を投入する企業に加え、当該製品の原材料や部品を供給する企業も、各製品カテゴリーにおける導入スケジュールを注視しつつ、DPP対応を計画的に進める必要があります。
DPPにおける共通の製品持続可能性パラメータ
DPPでは、ESPRの附属書I(Annex I)に記載された製品パラメータ(product parameters)に基づき、製品ごとの情報開示が求められます。これらのパラメータは、特定製品群に限定されず、あらゆる製品カテゴリに横断的に適用可能な基盤として位置付けられています。
たとえば、下表のような項目が含まれます。
これらの情報はQRコードやRFIDを介してデジタルで提供され、消費者、規制当局などの関係者が容易にアクセスできるように設計されています。
また、信頼性確保のため、第三者認証やブロックチェーン技術の活用も今後求められていくと見込まれています。
| カテゴリ | データポイント | 出典 |
|---|---|---|
| 再使用・修理等を妨げる技術の回避 | • 再使用/修理/リサイクルを妨げる技術設計の排除 | Annex I (e) |
| 懸念物質の使用 | • 懸念物質の名称 • 製品内の懸念物質の位置 • 濃度(%) | Annex I (f) |
| エネルギー・水・資源の使用量 | • エネルギー/水/資源のライフサイクル消費量 • 森林伐採への影響など • リサイクル材料の使用率:再生原料率 • 重要原材料の再利用率 • 再生可能原料の使用率:バイオ素材 • 持続可能林産物の割合 | Annex I (g)(h)(i) |
| 製品および包装の重量・体積 | • 製品重量/体積 • 製品-包装比率 • 軽量化設計(低密度材料/ハイブリッド材料の使用、機能統合) | Annex I (j)(t) |
| 環境フットプリント | • LCAを用いた環境影響評価値 • カーボンフットプリント • マテリアルフットプリント | Annex I (m)(n)(o) |
| 排出管理 | • マイクロプラスチック/ナノプラスチック放出量 • 大気/水質/土壌への排出量(騒音含む) • 廃棄物発生量(プラスチック/危険廃棄物) | Annex I (p)(q)(r) |
| 機能性能 | • 製品の意図された使用性能、使用上の注意事項、他製品/システムとの互換性 | Annex I (s) |
※本表は、ESPR Annex Iの内容を基に翻訳ツール等を用いて整理した参考資料です。実務的な理解を目的としており、法的な正確性については公式文書をご確認ください(エコデザイン規則(ESPR))。
日本企業が今すぐ対応すべき理由
DPPへの対応は、日本企業にとってリスクと機会の両方をもたらします:
① 【規制リスク】
DPPに対応できなければ、EU向け輸出が困難になる可能性があります。これは単なる書類対応ではなく、データ基盤の整備が必要です。
② 【コスト増リスク】
情報収集・可視化の初期コストは無視できません。しかし、逆に言えばトレーサビリティ体制の構築・IT化が進めば、中長期的には業務効率とブランド信頼性が向上します。
③ 【企業価値・投資影響】
ESPRやDPP対応の有無は、今後欧州をはじめとする投資家による評価軸の一つとなります。情報を戦略的に開示できる企業ほど、ESG評価で優位に立つ可能性があります。
④ 【競争優位性】
低炭素化・リサイクルの潮流が加速する中、DPP情報を収集することから新たに生まれるエコデザイン・新規事業展開が競争力の源泉となります。
まとめ:DPPはコストではなく“未来の資産”
DPPは単なる規制対応ではなく、企業の透明性と持続可能性を証明する「ビジネス資産」です。EUを皮切りに、アジアや北米でも類似の制度が広がることが予想されることから、早期対応が企業の競争力を左右します。
日本企業は今、DPPを戦略的に活用し、以下を目指すべきです:
- 情報基盤の整備:データ管理システムを構築し、作業工数を低減するとともに透明性を強化。
- エコデザインの推進:環境配慮型製品の開発方針の見直しを行いつつ、グローバル市場での存在感を確立。
- ステークホルダーとの対話:信頼性あるデータを通じて、消費者・企業・規制当局との関係を強化。
DPPへの対応を「リスクへの対応コスト」ではなく「将来への投資」として捉え、主体的に取り組む企業こそが、これからの国際市場をリードしていくでしょう。
出典
欧州委員会 Regulation (EU) 2024/1781:Ecodesign for Sustainable Products Regulation(ESPR)
欧州委員会 ESPR Working Plan 2025–2030
欧州委員会 European Green Deal Policy Overview