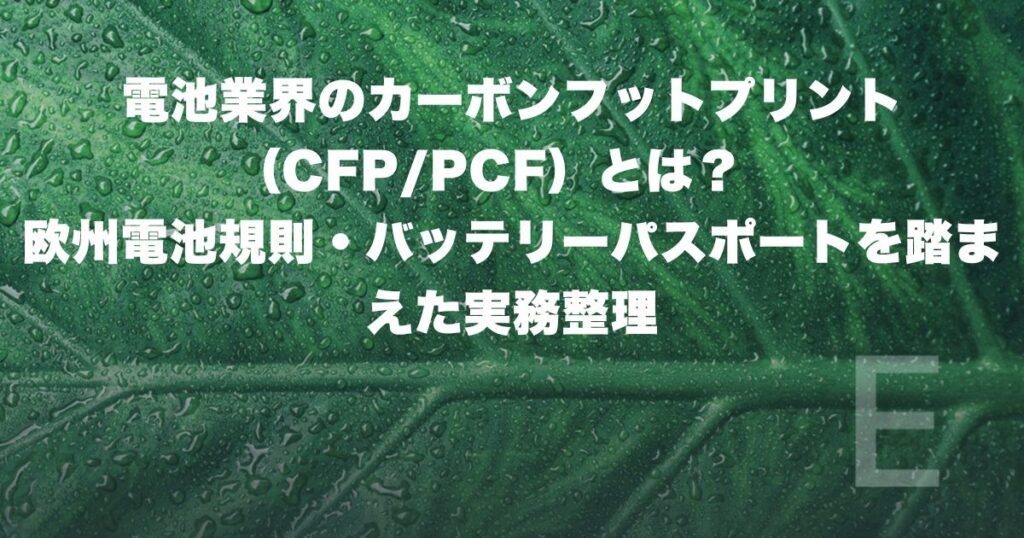
その他の記事一覧
注目記事
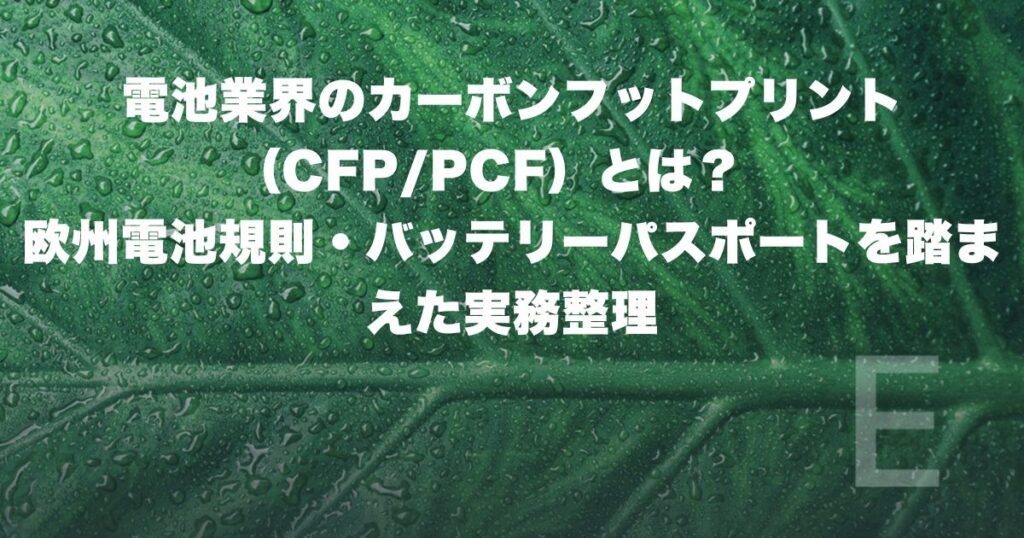
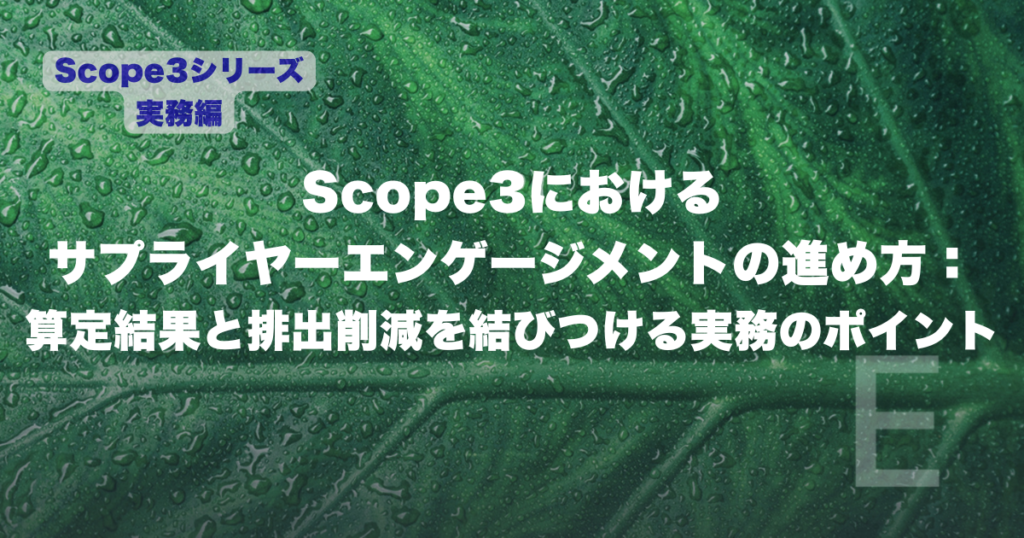
Scope3におけるサプライヤーエンゲージメントの進め方:算定結果と排出削減を結びつける実務のポイント
記事一覧
2025年12月ダイジェスト:IFRS財団サステナビリティ関連基準の採用状況
Scope3算定をどう設計するか~排出削減の取り組みと算定結果を結びつける考え方
なぜ今、Scope3が企業経営のテーマになっているのか?
Scope3とは?算定対象・15カテゴリをわかりやすく解説
Scope3算定はなぜ難しいのか 有価証券報告書・SSBJ開示で説明が難しくなる理由
金融審議会WG報告で何が決まったのか SSBJ開示と第三者保証の最新整理(2026年1月版)
サステナビリティ開示はなぜ企業価値を高めるのか? CSRD・SSBJ時代に求められる非財務情報開示の本質
【よくある質問】スコープ2と電力部門の会計に関する公開協議
IFRSサステナビリティ・シンポジウム2025 — 主要なポイント
今後のスコープ2公開協議:時間別マッチングと供給可能性
よくある質問
企業がサステナ評価を高めるためには、以下のような取り組みが効果的です。
・ESG情報の体系的な整備と開示(定量・定性)
・気候・人権・資源循環など重点テーマにおける戦略の具体化
・サステナビリティ委員会などガバナンス体制の明確化
・評価機関の質問票やスコア基準への適切な対応(例:CDP回答の質向上)
つまり、「実行しているだけでなく、きちんと伝える」姿勢が評価向上には不可欠です。
代表的なサステナ評価の指標・格付けには以下があります。
・CDPスコア(気候変動、水リスク、森林などのテーマ別)
・MSCI ESG Rating(企業をAAA〜CCCで格付け)
・FTSE4Good Index(ESGパフォーマンスが一定水準以上の企業)
・Sustainalytics(リスクベースのESG評価)
・EcoVadis(サプライチェーン対応に強み)
評価結果は、投資判断、調達基準、取引先管理などに広く活用されています。
サステナ評価とは、企業の環境・社会・ガバナンス(ESG)への取り組みを、評価機関が独自の基準でスコア化・格付けするものです。
評価基準は機関ごとに異なりますが、共通して重視される要素は以下の通りです。
・ESGリスクと機会への対応状況
・気候変動への戦略や目標(例:ネットゼロ、SBTなど)
・情報開示の透明性と一貫性(財務報告との統合など)
特に近年は、気候関連財務情報(TCFD)や人権デューデリジェンスの開示が評価に大きく影響しています。
SBT認証を取得するには、気候科学と整合した削減目標の設定が求められます。具体的には、
・スコープ1(自社の直接排出)とスコープ2(購入電力等の間接排出)については、1.5℃シナリオに合致する削減目標を設定
・スコープ3(サプライチェーン等のその他の間接排出)についても、排出量が一定割合を超える場合は、包括的な目標の設定が必須
また、SBTiはネットゼロ認証枠組み(Net-Zero Standard)も提供しており、より長期的な削減目標への移行も可能です。
SBTに認定されることで、企業は以下のようなメリットを得られます。
・脱炭素経営への本気度を対外的に示せる(信頼性向上)
・投資家・金融機関からの評価やESGスコアの向上
・サプライチェーン上の顧客や取引先からの信頼確保
・従業員や求職者への好印象や企業ブランディング強化
脱炭素の本気度を「見える化」し、競争優位につなげるツールとして活用されています。
SBT(Science Based Targets)認証とは、気候科学に基づいて企業が設定する温室効果ガスの排出削減目標を、国際的なイニシアティブ(SBTi)が審査・認定する制度です。
目標がパリ協定の「1.5℃目標」や「ネットゼロ」に整合しているかどうかを第三者が評価することで、企業の脱炭素戦略の信頼性を高めます。
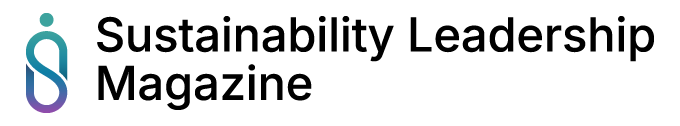

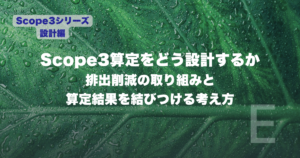


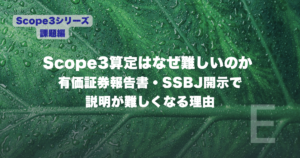
-300x158.png)



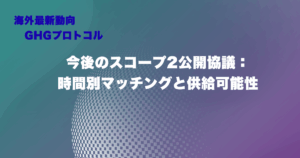
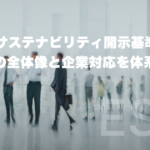

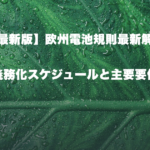
とは-―-製品のGHG見える化から企業全体の削減へ-150x150.png)
