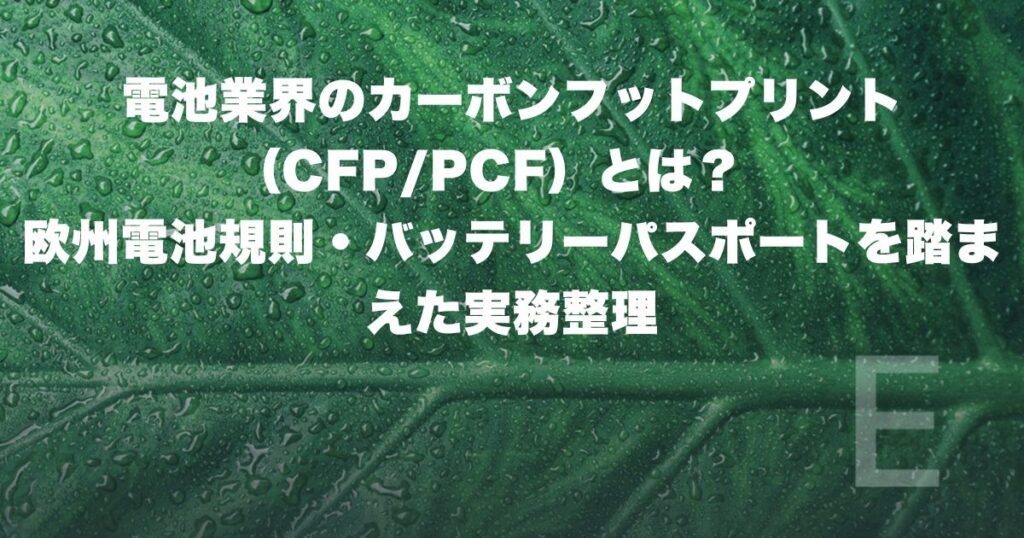
企業規制(海外)の記事一覧
注目記事
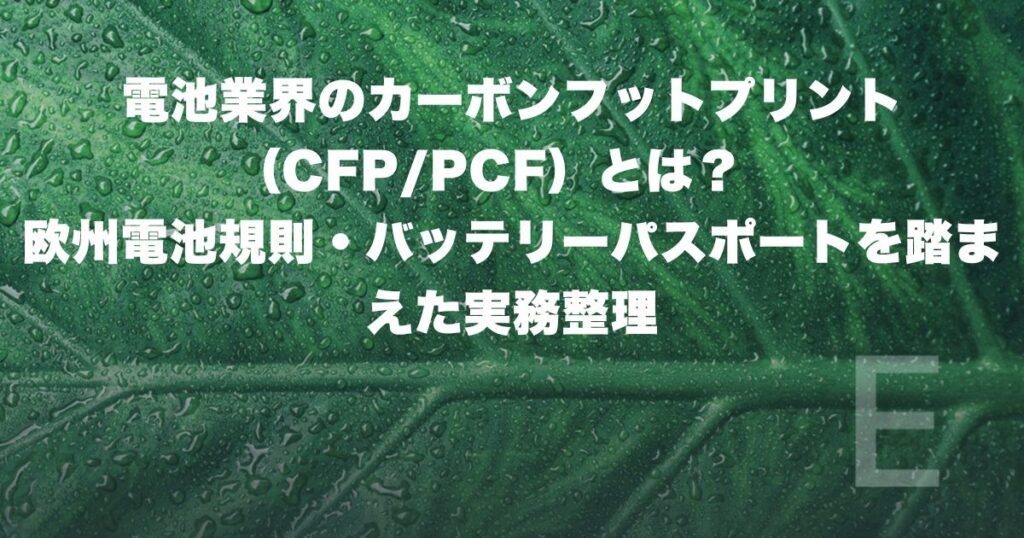
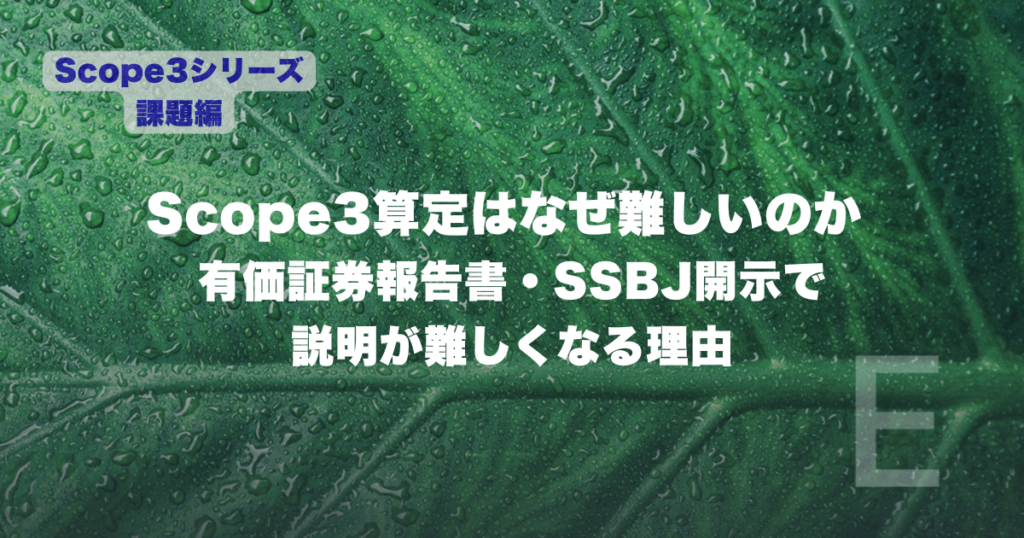
Scope3算定はなぜ難しいのか 有価証券報告書・SSBJ開示で説明が難しくなる理由
記事一覧
SSBJ・CSRD・IFRS S1/S2をどう読み解くべきか? 企業価値評価に使われるサステナビリティ開示の共通構造
サステナビリティ開示はなぜ企業価値を高めるのか? CSRD・SSBJ時代に求められる非財務情報開示の本質
欧州理事会はEUDR規制の簡素化と延期を目的とした改正案を承認
欧州電池規則:原材料デューデリジェンス(DD)義務の適用が延期
【最新版】CSRDとは? EU企業サステナビリティ報告指令・ESRS・対象企業・ダブルマテリアリティ・簡素化動向を整理する
企業価値向上のための“攻め”のサステナビリティ経営「Booostカンファレンス」開催レポート① トークセッション
企業価値向上のための“攻め”のサステナビリティ経営「Booostカンファレンス」開催レポート② 基調講演(1)BCG半谷氏&実務セッション
企業価値向上のための“攻め”のサステナビリティ経営「Booostカンファレンス」開催レポート③ パネルディスカッション&基調講演(2)一橋大学 野間教授
森林破壊規制の対象を絞った改訂:評議会が議会との協議開始準備完了
サステナビリティ報告とデューデリジェンス:欧州議会議員が簡素化変更を支持
よくある質問
SASB基準を活用することで、以下のようなメリットがあります。
・投資家が重視するESGリスクや機会を的確に伝えることができる
・財務との関連性が明確になり、企業価値とのつながりを示しやすい
・他社との比較がしやすくなり、国際的な資本市場での信頼性が高まる
結果として、投資家との対話の質が向上し、長期的な資本コストの最適化にもつながる可能性があります。
SASBとGRIは、いずれもサステナビリティ情報開示の国際的枠組みですが、対象読者と目的が異なります。
・SASBは主に投資家向けで、財務的に重要なESG情報にフォーカスしています。
・GRI(グローバル・レポーティング・イニシアティブ)は、広範なステークホルダー(従業員、顧客、地域社会など)向けで、社会的・環境的影響を包括的に開示することを目的としています。 つまり、SASBは“投資判断に役立つ情報”、GRIは“社会的責任の説明”を重視しています。
SASB(サステナビリティ会計基準審議会)の基準は、業種ごとに財務的に重要なサステナビリティ課題(ESG項目)を特定し、それに基づいた情報開示を促すものです。
米国証券市場における開示慣行や投資家ニーズを反映して設計されており、77業種に細分化された業種別スタンダードが特徴です。
IFRS S1およびS2は、2024年1月から適用可能(effective)とされていますが、導入時期は各国・地域の規制当局の判断にゆだねられています。
例えば、
・英国・カナダ・ナイジェリア・シンガポールなどでは、ISSB基準の導入を公式に表明しています。
・日本では、2025年3月5日にSSBJ(サステナビリティ基準委員会)がISSB基準に準拠した「SSBJ基準(第1号・第2号)」を公表しました。
つまり、グローバルでは導入が進む一方で、企業の所在地や上場市場によって準拠義務の有無が異なるため、自社がどの規制に該当するかを早期に把握する必要があります。
両者の違いは以下の通りです。
・IFRS S1は、企業が開示すべきサステナビリティ情報の基本的なルールを示したものです。環境・社会・ガバナンス(ESG)など、幅広いテーマが対象です。
・IFRS S2は、気候関連に特化した内容で、S1を補完する基準です。企業が気候リスクや機会をどのように捉え、対応しているかを詳しく報告することを求めています。
簡単に言えば、S1は「何を開示すべきか」の基本的な考え方を示し、S2は「気候」に関してより深掘りした情報を求める補完的な位置づけです。
IFRS財団は、国際サステナビリティ基準審議会(ISSB:International Sustainability Standards Board)を通じて、企業のサステナビリティ関連財務情報を統一的に報告するための基準を策定しています。
この枠組みは、既存の財務報告と整合させつつ、企業が中長期的に直面するサステナビリティリスクと機会を透明に開示することを目的としています。
具体的には、IFRS S1およびIFRS S2という2つの開示基準が発行されています。
EUDRに対応するためには、企業は次の3つの柱を中心とした体制整備が必要です。
①リスク評価とデューデリジェンス体制の構築
原材料の調達先における森林破壊リスクを識別・評価
②サプライチェーン全体の監査・管理
必要に応じてサプライヤーとの契約見直しや現地確認を実施
③製品ごとのトレーサビリティ確保(地理情報の提出)
原産地の地理情報の提出が義務化される場合もあります EU市場に輸出する企業だけでなく、間接的にEU向けサプライチェーンに関与する企業も対象になり得るため、早めの対応が推奨されます。
EUDRは、企業のサプライチェーンにおける森林破壊を未然に防ぐことで、以下のような持続可能な調達と環境保全を促進します。
・違法伐採や森林開発由来のリスクの排除
・森林生態系の保護と生物多様性の維持
・原産地の明確化(トレーサビリティの義務化)による透明性向上 このように、EUDRは単なるコンプライアンス対応ではなく、企業の責任ある調達戦略の一環として捉えるべき規制です。
EUDR(EU森林破壊防止規則:EU Deforestation Regulation)は、森林破壊や森林劣化と関連性のある一次産品およびその関連製品をEU市場に流通させる企業に対して、厳格なデューデリジェンスを義務づけるものです。
対象となる主要な製品は以下の7品目です。
①牛、②カカオ、③コーヒー、④アブラヤシ、⑤ゴム、⑥大豆、⑦木材の7つの関連商品を含むこれらの関連製品(牛肉、チョコレート、パーム油、タイヤ等)
CSRDでは、欧州サステナビリティ報告基準(ESRS)に基づいた詳細な情報開示が求められます。主な項目には以下が含まれます。
・ESGリスクと機会の特定・管理方針
・バリューチェーン全体での影響評価(自社だけでなく取引先も含む)
・ダブルマテリアリティ分析
① 企業が社会や環境に与える影響(インパクト・マテリアリティ)
② ESG課題が企業の財務に与える影響(財務マテリアリティ)
・脱炭素戦略、社会的責任、ガバナンス体制などの定量・定性情報
CSRDは単なる報告義務ではなく、企業の戦略・ガバナンス・リスク管理の一体的な見直しを求める枠組みです。
CSRDは2024年から段階的に適用されますが、一部の企業については「オムニバス指令(Omnibus Directive)」によって報告義務の開始時期が延期されました。
詳細は本ページの下部をご確認ください。
CSRDは、「企業サステナビリティ報告指令(Corporate Sustainability Reporting Directive)」の略で、EUが制定した企業向けのサステナビリティ情報開示に関する法令です。 この指令は、企業に対して環境・社会・ガバナンス(ESG)に関する非財務情報を、統一された基準に基づいて報告することを求めています。目的は、投資家やステークホルダーが企業の持続可能性を正確に評価できるようにすることです。
CSDDDに準拠するためには、企業は以下のプロセスを構築・運用する必要があります。
・人権・環境リスクの特定と評価(サプライチェーン全体)
・リスクに対する予防・是正措置の実施
・デューデリジェンス方針と手順の整備
・年次報告書の作成と情報公開
・ステークホルダー(従業員、NGOなど)との継続的な対話
対応が不十分な場合、行政制裁や損害賠償請求の対象になるリスクがあるため、特にEUと取引のある日本企業は早期対応が求められます。
CSDDDの大きな特徴は、以下の3点です:
・人権と環境の両方にフォーカスしていること
・サプライチェーン全体に法的責任が及ぶこと(取引先も含む)
・義務違反に対する制裁(罰則や損害賠償請求)の導入
たとえば、CSRD(企業持続可能性報告指令)は主に「情報開示」を目的としていますが、CSDDDはより実践的で、行動の義務が伴う点が異なります。
CSDDD(企業持続可能性デューデリジェンス指令:Corporate Sustainability Due Diligence Directive)は、EUが制定した法令で、企業に対して人権と環境に関するデューデリジェンスの実施を義務づけることを目的としています。
これにより、グローバルサプライチェーン全体における労働環境・人権侵害・環境破壊などのリスクを事前に把握・防止し、より持続可能で責任ある企業活動の実現を促進します。
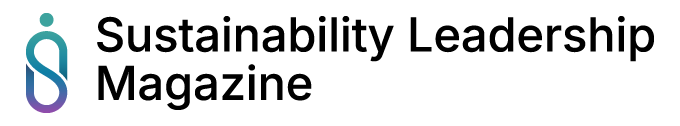
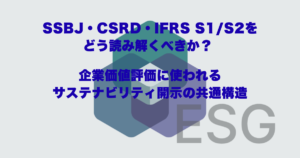

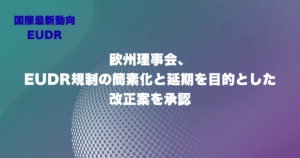
義務の適用が延期-300x158.png)


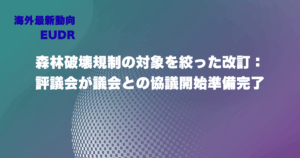

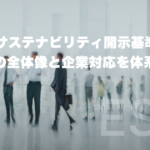

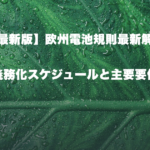
とは-―-製品のGHG見える化から企業全体の削減へ-150x150.png)
