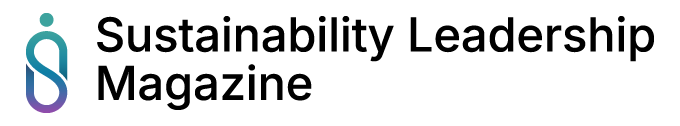削減貢献量 -3つの適格性ゲートを通過するために
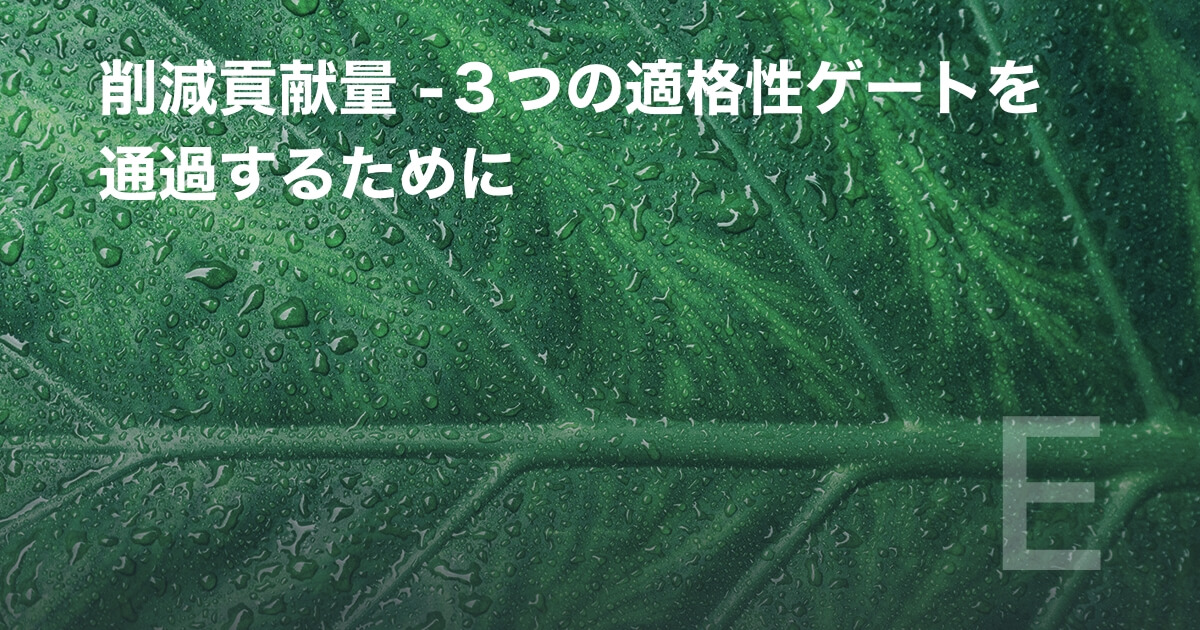
目次
以前の記事「削減貢献量 -3つの視点から活用意義を見る」で、削減貢献量の概要と、企業・投資者・顧客の3つの視点から見た活用意義を解説しました。 本記事では、 持続可能な開発のための経済人会議(WBCSD)が発表した「削減貢献量の算定・開示に関するガイダンス(Guidance on Avoided Emissions)」の中で示された「適格性ゲート」に焦点を当て、それぞれを通過するための鍵について解説します。
削減貢献量の位置づけ
本題に入る前に、まず削減貢献量が脱炭素化領域の中でどのように位置づけられているのかを整理しておくことが重要です。これは、後述する適格性ゲートの考え方にも深く関係しています。
下図のように、同ガイダンスの中では、企業のネットゼロに向けた取り組みを3つのピラーに分類し、その優先順位が明示されています。削減貢献量はピラーBに位置づけられていますが、その前提となるのがピラーAである自社のGHG排出量削減に取り組むことです。一方で、自社の排出削減努力を十分に行わずにピラーBやピラーCに注力することは、受け入れられにくいと考えられます。

企業の脱炭素化への潜在的な貢献とガイダンスの焦点(WBCSD Guidance on Avoided Emissionsを基にBooost作成)
3つの適格性ゲート
削減貢献量の主張の正当性を判断するため、同ガイダンスでは「3つの適格性ゲート」が設定されています。
ゲート1「気候変動対策の信頼性」
前述の通り、企業が削減貢献量を主張するためには、まず自社の気候変動対策が十分でなければなりません。自社の排出削減努力が不十分なまま、削減貢献量のみを強調することは、グリーンウォッシュと見なされるリスクが伴います。 具体的には、最新の気候科学に基づいた戦略の策定・開示、Scope1・2・3排出量の算定と目標設定、そして透明性の高い進捗報告が求められます。
■通過するための鍵
- 自社Scope1・2・3排出量について、算定ルールの策定または見直しを含め、定期的に算定を行う ※外部保証を取得することで、信頼性が高まる
- 科学的根拠に基づく削減目標を設定し、SBT(Science Based Targets)認証を受ける
- 削減貢献量に関する主張は、これらの取組みが土台として整っていることが前提であると社内の共通認識を持つ
ゲート2「気候変動に関する最新の科学との連携」
削減貢献量の対象となるソリューションが、最新の気候科学に照らした気候変動を緩和する効果があるかが問われます。 参照基準としてIPCC(気候変動に関する政府間パネル)の第6次評価報告書(AR6)やEUタクソノミーが挙げられています。さらに、1.5℃目標と整合的でない化石燃料の探査・採掘・流通などに直接関与する活動は原則として適格性から除外されています。
■通過するための鍵
- ソリューションが化石燃料関連の活動でないことを確認する
- 参照した科学的根拠のバージョンや数値を明示する
- 気候科学の動向を定期的に確認する
ゲート3「貢献の正当性」
このゲートでは、企業が主張する削減貢献量が直接的かつ顕著なGHG排出量削減インパクトを持つかが評価されます。この基準を設けることで、ネットゼロの実現に必要なイノベーションの促進や開発規模の拡大を促すと同時に、主張の高い信頼性を確保することを目的としています。 GHG排出量削減インパクトとして、省エネ技術の導入によるエネルギー消費量の削減や、再生可能エネルギーの活用による化石燃料依存度の低下などが挙げられます。その効果は、客観的なデータに基づいて立証する必要があります。
■通過するための鍵
- 効果立証の根拠となる実証データ(導入前後のエネルギー消費量やGHG排出量等)を収集・蓄積する
- 削減効果がライフサイクルのどの段階で発生しているかを明確にする
- 削減効果が自社のソリューションに起因することを示すため、他要因(顧客の行動変化や他製品の併用など)との影響を区別する
主張前に通るべき扉
削減貢献量は、企業の環境価値を示す新たな指標として期待されています。その誤用を避けるためには、主張に先立ち、適格性を確認しなければなりません。WBCSDのガイダンスで示された3つの適格性ゲートは、企業の削減貢献量が社会的に意味のあるものかを判断するフィルターの役割を果たします。これらを通過することで、定量化、実績アピールへと進むことができます。