削減貢献量 -3つの視点から活用意義を見る
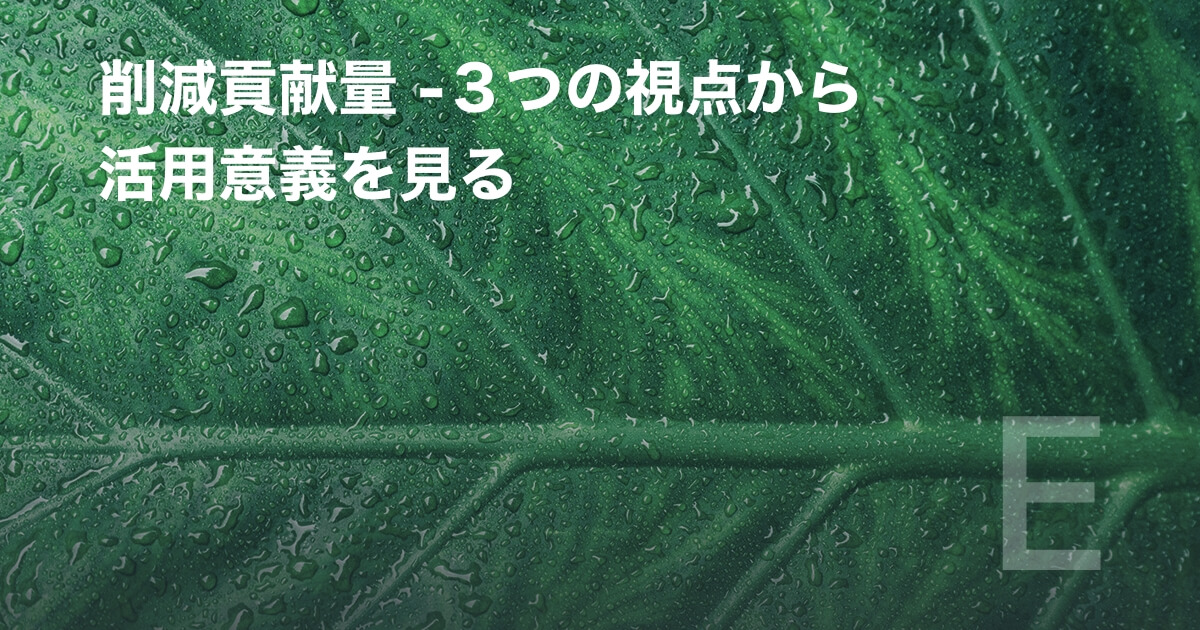
目次
脱炭素への取り組みが活発化する中、これまで自社の排出削減に注力してきましたが、事業成長に伴い、製品・サービスの生産・販売が拡大すると、GHG排出量も増えてしまうという課題を感じている企業は少なくありません。そうした中で、技術・サービスの革新によって実現されるGHG削減効果を定量的に可視化する「削減貢献量」という概念が注目を集めています。
本記事では、削減貢献量の概要と算定・開示方法の動向を整理したうえで、その活用意義を3つの視点からご紹介します。
削減貢献量とは
削減貢献量とは、従来使⽤されていた製品・サービスを新たに開発した製品・サービスで代替することによって削減されるサプライチェーン上の排出量のことです。
GHGプロトコルのScope1、2、3と異なり、削減貢献量は、「社会へのポジティブなインパクト」に着目し、事業者の新たな低炭素ソリューションが他者の排出量をどれだけ削減できたかを評価する指標です。一部メディアではScope4と説明していますが、正式にはまだリリースされてはいません。
.png)
削減貢献量のイメージ(WBCSD Guidance on Avoided Emissionsを基にBooost作成)
算定・開示方法の動向
日本では、電機電子や都市ガスなどの業界団体が削減貢献量の算定・開示方法について独自ガイダンスを策定しており、川崎市や滋賀県など一部の地方自治体も削減貢献量に関する制度運用を開始しています。海外では、持続可能な開発のための経済人会議(WBCSD)と国際化学工業協会協議会(ICCA)が化学業界における削減貢献量の算定方法を示しています。
ただこれらのガイダンスは特化したものが多く、算定方法の統一には至っていませんでしたが、2023年にWBCSDが日本政府との連携のもと、「削減貢献量の算定・開示に関するガイダンス(Guidance on Avoided Emissions)」を発表しました。横断的かつ透明性を重視するのが特徴であり、信頼性の高い国際的なフレームワークとして削減貢献量の実用化を後押ししています。
活用意義
ここでは、企業、投資者、顧客の3つの視点から、削減貢献量の活用意義を探ります。
1. 企業の成長を牽引するきっかけ
削減貢献量の活用は、企業の脱炭素技術開発を成長戦略と結びつける手段となります。企業成長を維持しながら脱炭素を実現するには、業務改善だけでは限界があります。削減貢献量の活用により、製品・サービスの削減効果を可視化し、技術イノベーションを環境価値として打ち出すことができます。 例えば、パナソニックは、省エネ製品や電化製品の拡販を通じて顧客のエネルギー使用量を削減し、社会全体のGHG削減に注力しています。2023年度には削減貢献量の対象事業を56事業に拡大し、約3,697万トンの削減貢献量を創出しました。更に、同社は長期環境ビジョン「Panasonic GREEN IMPACT」において、既存事業に加えて新技術・新事業による削減貢献量の目標も明示しており、削減貢献量を環境戦略と企業成長の中核に位置づけています。 このように、削減貢献量の活用は、企業にとって脱炭素と成長の両立させる新たな戦略の礎となり得ます。
2. 環境価値を資本とつなぐ指標
削減貢献量は、投資者に企業の環境価値を定量的に伝える手段と機能します。サステナブル投資が加速する中、投資者は企業の環境へのポジティブな影響を評価する指標を求めています。削減貢献量に取り組むことで、新たな市場の確立や成長性が客観的に見込まれるため、ESG投資やグリーンボンドなどの資金調達においても有利に働きます。 野村アセットマネジメントは、2023年から削減貢献量を日本企業のESGスコアにおける評価項目の一つに組み込んでいます。具体的には、企業が開示する削減貢献量に同社の独自内部炭素価格を乗じて、その経済価値と営業利益に対する比率を計算し、企業の気候関連機会として評価しています。 こうした動きは、削減貢献量が投資の世界においても企業価値を測る新たな指標として浸透し始めていることを示しています。
3. 顧客の環境意識に応える
削減貢献量を正確に算定・開示することは、企業のブランド価値を高め、消費者や法人顧客を惹きつける要素です。 消費者にとって、削減効果の開示は環境への配慮の裏付けとなり、製品・サービスを選ぶ際の明確なインセンティブとなります。一方、法人顧客にとっては、取引先が削減貢献量を開示していることで、グリーン調達の対応がしやすくなり、企業間の信頼構築やサプライチェーン上での優位性確保にも寄与します。 例えば、メルカリは、衣類、電子機器、本などの6つのカテゴリーを対象に、中古品を新品の代替として購入した場合の削減貢献量を算出しています。算出に当たって、単なるモデル計算にとどまらず、ユーザーアンケートから使用頻度や使用年数等を用いて推計している点が特徴的です。これにより、ユーザーに日常の行動が社会的インパクトにつながっていることを実感させ、サービスの利用継続と環境意識の向上を促す好循環が生まれます。
削減貢献は環境価値の軸へ
ネットゼロの実現には、自社排出削減だけでは限界があることが明らかになってきました。削減貢献量は従来のGHGインベントリの限界を補完する考え方であり、企業の課題解決力を示す取り組みです。 今後、削減貢献量の浸透が進む中、これをいかに活用するかが、企業の環境価値を左右する新たな評価軸になると考えます。
出典
環境省 【参考①】削減貢献量について
一般社団法人 電子情報技術産業協会 電機・電子業界 カーボンニュートラル行動計画 実施要領
一般社団法人 日本ガス協会 都市ガス業界の温室効果ガス削減貢献量算定ガイドライン
川崎市(環境局 )「川崎市脱炭素ライフスタイル行動変容促進プロジェクト」を 立ち上げました!
滋賀県 製品等を通じた貢献量評価手法
WBCSD, ICCA Avoiding greenhouse gas emissions: the essential role of chemicals
WBCSD Guidance on Avoided Emissions
パナソニックホールディングス株式会社 環境:中長期環境ビジョン
GXリーグ 削減貢献量 -金融機関における活用事例集-
株式会社メルカリ メルカリのポジティブインパクト(削減貢献量)
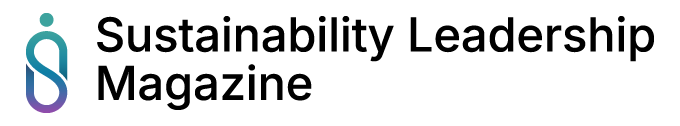
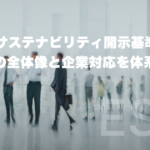

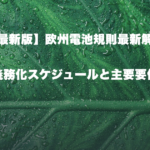
とは-―-製品のGHG見える化から企業全体の削減へ-150x150.png)
