SSBJ対応部署必読・求められるサステナビリティ経営は何か?

目次
「失われた30年」とも形容される日本経済の停滞。バブル崩壊後、構造改革や制度の見直しが進まない中で、古い価値観=悪という見方が定着しつつあります。利益や資産価値などの評価に加えて非財務面での取組みが求められる中、サステナビリティ経営の潮流と、求められる主要なテーマについて解説します。
21世紀型経営への変化要請
かつての日本企業は、終身雇用や年功序列、地域密着型の経営など、安定性と内部秩序を重視した経営スタイルを築いてきました。これらは高度経済成長期を支える礎となり、特に従業員や地域社会を重んじる姿勢は、今日のサステナビリティ経営の原型と見ることもできます。一方、環境破壊や気候変動、人権問題など、SDGsに代表されるグローバルでの社会課題が複雑化した21世紀においては、これまでの価値観だけでは持続可能な成長を実現するのが難しくなっています。従来の「社会貢献」や「CSR活動」にとどまらず、脱炭素への取り組みやサプライチェーン全体での排出量管理、人的資本などを通じて、非財務活動を企業価値向上に連動させていくことが求められています。
サステナビリティ経営で求められること
サステナビリティ経営では、以下の6つの変化を同時に実施することが求められています。
1.経営戦略の再構築
ESG、サステナビリティ活動を単なるリスク回避ではなく、新たな成長の機会の一つとして経営戦略に取り込み、中長期思考もとづく経営判断の実施
2.組織・ガバナンスの改革
取締役会による非財務情報の監視・監督がもとめられ、多くの企業ではサステナビリティ委員会などの専門組織を設置。さらには非財務活動を経営戦略に組み込むために、組織を横断した連携が必要
3.非財務情報のマネジメントと開示
非財務情報は任意開示から制度開示へ移行中。制度開示では財務情報に加えて、気候変動や自然資本、人的資本、人権などの非財務情報を、国際基準(IFRS、TCFD、TNFDなど)に則った開示が求められいると同時に、これらの指標の改善が不可欠。任意開示と制度開示での開示内容の整理が不可欠。
4.ビジネスモデルの変革
環境破壊や気候変動、グローバルな人権問題などに対応するための、カーボンニュートラル・循環経済モデルへの移行やサプライチェーン全体に対する責任ある調達などが必要。事業成長をサステナビリティが牽引するビジネスモデルの設計が不可欠
5.人材・企業文化の変革
これらを推進するためには社員の意識変革が必要であると同時に多様な人材を活用する「人的資本経営」との連動も重要
6.ステークホルダーとの対話と共創
投資家はもちろん、従業員、地域社会、消費者、NPO等との建設的な対話を行い、「社会の信任があってこと自社が成り立つ」という考えが必要
まとめ
サステナビリティ経営は、単なる環境保護活動やCSR活動とは異なり、企業の存在意義(パーパス)、成長戦略、オペレーションなどを将来社会の制限の下で再設計する変革を意味します。この変革は一朝一夕には実現できないため、変化し続けることが必要です。サステナビリティ担当役員には経営者の一員として、規制対応にとどまらないサステナビリティ経営のリーダーシップが求められています。自社の歴史や文化を資産と捉え、そこから生まれる技術や企業特性は国際的な競争力へとつながる可能性があります。そこにこそ、サステナビリティ経営の真の競争力が宿ると言えるでしょう。
出典
価値協創のための統合的開示・対話ガイダンス2.0(価値協創ガイダンス2.0)_経済産業省 20220830_2.pdf
サステナビリティ(気候・事前関連)情報開示を活用した経営戦略立案のススメ_環境省_2025年3月 ~TCFDシナリオ分析と自然関連のリスク・機会を経営に織り込むための分析実践ガイド ver2.0~ 000308778.pdf
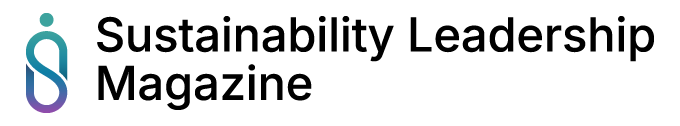


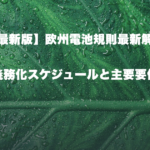
とは-―-製品のGHG見える化から企業全体の削減へ-150x150.png)
