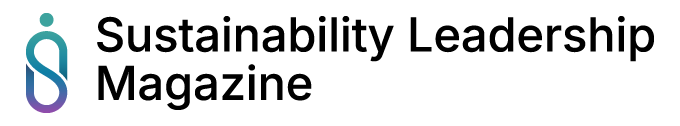削減貢献量 -算定ステップと報告要件を解説
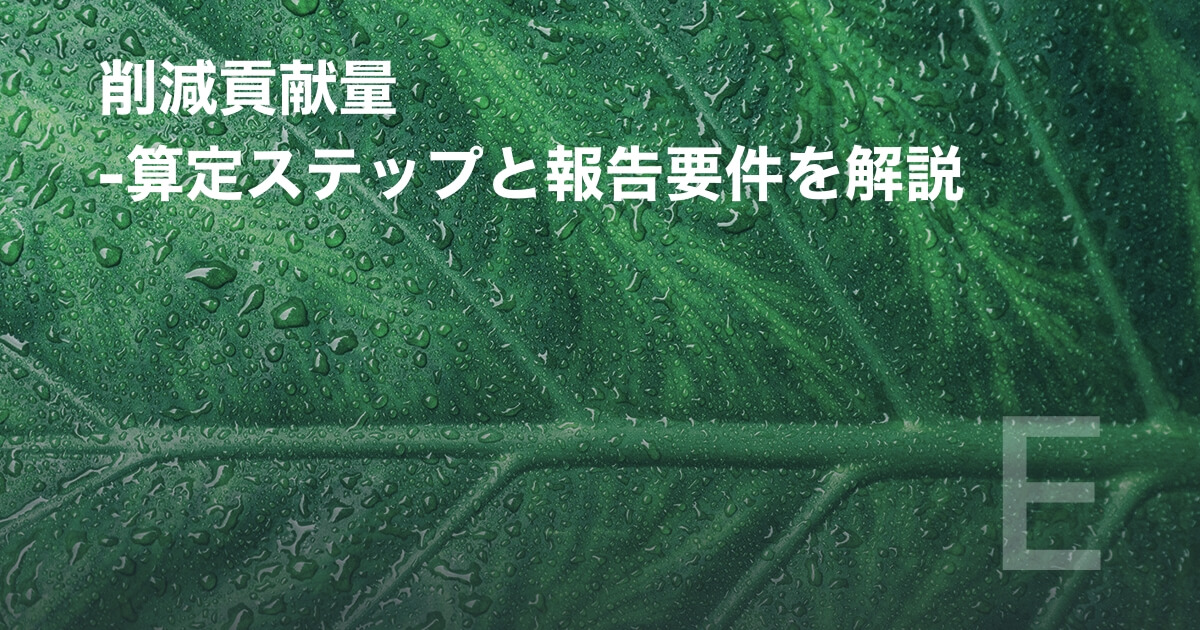
目次
前記事では、削減貢献量における3つの適格性ゲートとそれぞれを通過するための鍵を解説しました。今回は、 WBCSDが発表した「削減貢献量の算定・開示に関するガイダンス(Guidance on Avoided Emissions)」の中で示された「5つの算定ステップ」と「9つの報告時要件」について整理します。
5つの算定ステップ
適格性ゲートを通過した企業とそのソリューションについて、削減貢献量を定量化するための5つの算定ステップが定義されています。
ステップ1 タイムフレームの設定
まず行うべきは、「どのような時間軸で排出削減効果を評価するか」を明確にすることです。同ガイダンスでは、算定方法として2つのアプローチが提示されています。
1つ目は「フォワード・ルッキング(Forward-looking)型」で、ソリューションのライフサイクル全体の排出削減効果を、販売年に一括して算定する手法です。B2Cやソリューションの使用状況を追跡しない場合はこの方式が適しています。
2つ目は「イヤー・オン・イヤー(Year-on-year)」型で、使用状況に基づいてGHG排出量を販売年から毎年算定する手法です。B2Bやソリューションの使用状況を特定期間中に把握できる場合はこの方式が適しています。
ステップ2 参照シナリオの決定
ソリューションが導入されなかった場合、代替として最も可能性の高い参照シナリオを設定します。参照シナリオを決める際は、ソリューションが新たな需要の創出か既存需要への対応か、既存製品の改良か完全な置換か、また関連する法規制の有無などの要素を踏まえ、客観的かつ現実的な前提に基づいて設定することが求められます。過剰に有利な仮定を置いてしまうと、削減効果が過大に評価され、グリーンウォッシュと受け取られるリスクがあります。結果として、信頼の低下やレピュテーションリスクにつながりかねません。
ステップ3 ライフサイクルでのGHG排出量の算定
次は、ソリューションと参照シナリオの双方について、原料調達から廃棄までのライフサイクルGHG排出量を算定します。以下2つの算定アプローチが選択できます。
帰属的アプローチ:ソリューションのライフサイクル排出量の絶対値を算定
結果的アプローチ:特定の意思決定や行動によって引き起こされる排出量を算定
ステップ4 削減貢献量の算定
ステップ3で算出した参照シナリオの排出量からソリューションの排出量を差し引いて削減貢献量を算定します。削減貢献量は複数年にわたって推定されるのが基本的であるため、算定にあたっては、時間の経過に伴う状況の変化、例えばエネルギー利用状況や市場変化などの観点を考慮する必要があります。
ステップ5 企業単位での削減貢献量の算定(任意)
複数のソリューションで算定された結果を企業規模の削減貢献量として集計します。
9つの報告時要件
5つのステップを経て削減貢献量を算定した後、その結果を外部に報告・開示する場合は、同ガイダンスでは、下記9つの要件に従った報告が求められています。
| 1 | GHGインベントリや炭素吸収、移行のための財政的貢献と区別して報告しなければならない |
| 2 | カーボンニュートラルの主張に利用してはいけない |
| 3 | ソリューションレベルで外部に報告する際、ソリューションの説明とライフサイクルでのGHG排出量、参照シナリオを明記する |
| 4 | 「フォワード・ルッキング」、「イヤー・オン・イヤー」のいずれかのタイムフレームを用いたか明記する |
| 5 | 「3つの適格性ゲート」を通過したことを証明する |
| 6 | ソリューションが自社売上の何パーセントを占めるのか明記する |
| 7 | 第三者検証の有無を記載する |
| 8 | 環境対してソリューションによる負の影響がある場合は対策を開示する |
| 9 | リバウンド効果を評価に含めたかどうか、またその軽減策について明記する |
上記要件に加えて、参照シナリオの根拠や算定に使用された情報源と仮説、結果の不確実性などについても、社内で把握・管理する必要があります。
確かな価値にするために
削減貢献量は、企業の環境価値を社会に示す新たな指標ですが、その取り組みには、適格性の確認から算定、報告に至るまで多くの準備と判断が求められ、一足飛びには進みません。WBCSDのガイダンスが定義した3つの適格性、5つの算定ステップと9つの報告要件をを丁寧に踏むことで、脱炭素への貢献と環境価値を信頼性のある形で社会に伝えることができます。