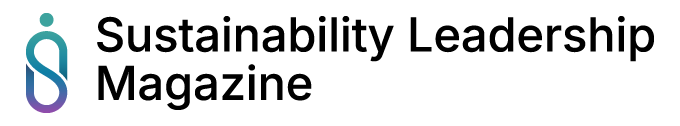中国のESG開示ーA株指針が導くサステナビリティ

目次
多くの日本企業が中国にサプライヤーを持ち、持続可能性への関心が高まる中、中国のESG情報開示規制が注目されています。グリーン製品認証や温室効果ガス排出量の公表、気候変動対策の導入など、サステナビリティを軸とした法制度整備が進んでいます。
ただし、中国は、ESG情報開示の全国統一義務化は未整備で、多くの法規は草案段階や試験運用に留まっています。制度の方向性は見えつつありますが、適用時期や対象範囲は流動的で、企業の実務対応には不確実性が伴います。
この様な状況下で、2025年度から適用される「A株ESG情報開示指針」が注目されています。本記事では、この指針の概要、対象企業、開示要件を整理し、日本企業にとっての示唆を探ってみます。
A株ESG情報開示指針:対象企業と適用スケジュール
中国政府は、ESG情報の透明性向上を目指し、上場企業を対象に段階的な開示義務化を進めています。その中核となるのが、2024年に施行され、2025年度から実質的に義務適用が始まる「A株ESG情報開示指針」です。
本指針は以下の条件に該当する企業を対象としています(法的根拠:第1章 第3条):
- 上証180指数に採用されている企業(大型・高流動性企業)
- 科創50指数に採用されている企業(新興企業中心の代表企業群)
- 中国国内外で同時に上場している企業(H株を含む)
これらは国際投資家からの注目度も高く、ESG開示の「リーダー企業」として先行的な役割を担うことが期待されています。該当企業は、2026年4月30日までに、2025年度の「上場企業サステナビリティ報告」または「ESG報告」を、上場先である上海証券取引所または深圳証券取引所に提出する必要があります。2025年4月時点で、その数は約458社に達しており、市場を代表する中核的な企業群と位置づけられています。(※21世紀経済報道より)。
開示項目の概要:ISSBベースで構成、Scope1・2排出量が義務化
本指針で定められたESG開示項目は、ISSBのフレームワークを基に策定されており、以下のような気候関連項目が明示されています。
| 開示項目 | 開示要求 | 概要 |
|---|---|---|
| 開示要点11:気候関連の財務影響 | 強制開示 | 気候関連要因が会社の財務状況、経営成果、キャッシュフローに与える影響を分析する。 |
| 開示要点15:気候関連目標 | 強制開示 | 会社が設定した気候関連目標(具体的な内容、適用範囲、期限)について説明する。 |
| 開示要点16:気候関連目標の達成進捗 | 強制開示 | 気候関連目標の達成状況と報告期間内の進捗を記載する。 |
| 開示要点17:温室効果ガス排出量 | 強制開示(Scope1,2) 推奨開示(Scope3) | 会社のGHG排出量(スコープ1・スコープ2)を開示し、スコープ3の開示は推奨。また、排出量の算定方法および第三者保証の状況を報告。 |
| 開示要点18:温室効果ガス削減実施 | 強制開示 | 会社の削減目標、施策、実際の効果と具体的な削減量を記載する。 |
これらの項目は一定の専門性を伴いますが、開示要件自体は過度に複雑ではなく、企業にとって比較的取り組みやすい内容となっています。現在はまだ実際のデータポイントや開示様式の細則が出揃っていないものの、制度自体はISSB/IFRS、SSBJとも整合性があり、国際整合性が意識された内容となっています。
GHG排出量開示の現状:2024年調査から見える課題
「2024年中国上場企業Scope 3情報開示研究」によると、中国本土および香港の上場企業約667社を対象に、Scope 3排出量の開示状況が分析されています。その主な調査結果を、以下に示します。
- 開示率:Scope 1・2の開示率は84%に達する一方、Scope 3は約80%の企業が未開示とされている。

図1:2024年企業Scope 1・2開示状況 図2:2024年企業Scope3開示状況
- 基準の採用:開示企業の60%がGHGプロトコル、20%がISO 14064を参照。12%のみがカテゴリ別に詳細を開示。
- 算定の透明性:Scope 3算定方法を開示する企業は30%未満。
- 重要カテゴリの不足:金融業界のScope 3開示率は35%だが、カテゴリ15(投融資関連排出)の開示は7%未満。カテゴリ1(購入商品・サービス)の開示も7%に留まる。
- 第三者検証:Scope 3を開示した144社のうち、第三者検証を実施したのは23%。
- 削減目標の設定:Scope 3削減目標を設定した企業は5%未満、ネットゼロ目標は3%のみ。
これらの結果から、サプライチェーン排出(Scope 3)の開示、目標設定は依然として課題が多く、透明性や詳細度の向上が必要と思われます。
まとめ:中国ESG対応の課題と戦略
2025年からのScope 1・2開示義務化に伴い、日本企業にとって中国市場でのESG対応は新たな段階に入ります。特に、A株に上場する日系企業の現地法人を含む対象企業は、直接的な合規対応が求められます。中国に顧客を持つ日本企業にとっても、Scope 3の推奨開示に備えたサプライチェーン管理の準備が重要となります。
日本企業は、中国の急速な法改正や消費者・NGOの監視強化といった現地特有の課題に直面しますが、TCFDやSSBJに基づくESG開示の経験を活かし、A株指針への対応を効率化できます。特に、グローバルサプライチェーン管理のノウハウはScope 3データ収集の強みとなります。一方、従業員流動性や現地サプライヤーのデータ透明性不足は障壁となるでしょう。Scope 3は現時点で推奨だが、国際的な義務化拡大に伴い、将来的に必須となる可能性が高いでしょう。
日本企業には、以下の対応策の実施が必要でしょう。
- 日本でのESGノウハウと現地コンサル協力を融合
- Scope 3算定のためのデジタルツール導入
- 現地従業員へのESG研修強化
A株指針は標準化されたフレームワークとして、信頼性ある開示の基盤を提供されます。中国のESG開示は発展途上ですが、上記対応を実施していくことで先行者利益を確保し、持続可能な成長の機会を得られることでしょう。
出典
CCEI 2024年中国上場企業Scope 3情報開示研究報告
上海証券取引所 上海証券取引所 上場企業自律監管指引 第14号──サステナビリティ報告(試行)
21世紀経済報道 A股ESG信披ルール、初年度の対象企業は458社