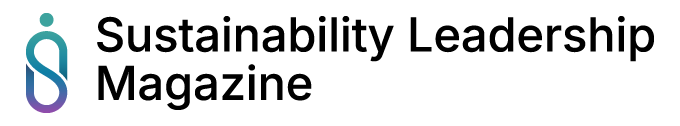シングルマテリアリティとダブルマテリアリティ:開示基準の違いが変えるサステナ経営の実務

目次
別記事「サステナ経営を実践する組織デザイン」では、CFO・CIO・CSOの連携によってシングルマテリアリティの実装を進める企業の組織デザインを紹介しました。
本記事では、その前提となる「マテリアリティ(重要性)」の考え方、すなわちシングルマテリアリティとダブルマテリアリティの違いを整理し、日本企業が直面する制度的要請と国際潮流の両面から読み解きます。
マテリアリティとは何か─サステナ経営の基盤概念
マテリアリティ(Materiality)とは、企業がどのサステナビリティ課題を重要と位置づけ、経営判断や情報開示に反映させるかを決める基準のことです。 近年は、投資家や規制当局のみならず、従業員、取引先、地域社会など多様なステークホルダーがこの重要性の定義を注視しています。 その中核となるのが、シングルマテリアリティ(Single Materiality)とダブルマテリアリティ(Double Materiality)という二つの視点です。
シングルマテリアリティ─SSBJが採用する企業価値中心の視点
シングルマテリアリティは、環境・社会要因のうち「企業の財務状況や企業価値に影響を与えるもの」を重要とみなす立場です。 2025年に公表されたSSBJ基準はこの考え方を採用しており、投資家の意思決定に資する財務的観点からの開示を求めています。つまり、温室効果ガス排出量や人的資本といったテーマも、「企業価値への影響」という観点で評価・開示することが前提となります。 この枠組みは、CFOを中心とした財務・非財務統合経営を推進する上で実務的に整合性が高く、別記事で紹介した「CxO連携モデル」を支える理論的基盤ともいえます。
ダブルマテリアリティ─GRIに端を発し、EUが制度化した双方向の重要性
一方で、ダブルマテリアリティは、企業が社会や環境に与える影響(インパクトマテリアリティ)と、社会・環境から受ける影響(ファイナンシャルマテリアリティ)の両面を重要とする立場です。この考え方は、もともとGRI(Global Reporting Initiative)が提唱した「企業の社会的影響の重要性」を基礎としており、その後EUがCSRD/ESRSにおいて制度的に採用しました。
たとえば、短期的には財務影響を伴わない人権侵害や地域社会への影響も、社会的に重大であれば「開示すべき重要課題」とみなされます。 このアプローチを採用することで、企業は「社会的価値の創出」と「企業価値の持続的成長」を一体的に捉えることが可能になります。 実際、日本企業の多くでダブルマテリアリティの枠組みを採用していることが、統合報告書やサステナビリティレポート等から読み取れます。
日本企業が抱える二重構造─制度開示と戦略開示の分岐点
現状、日本企業の多くで「シングルマテリアリティによる法定開示」と「ダブルマテリアリティによるステークホルダー報告」の二重構造に直面しています。 SSBJ準拠の有価証券報告書では、投資家視点での財務的影響を中心とした開示が求められますが、統合報告書やサステナビリティ報告書では、企業の社会的インパクトを含む広範な情報が期待されます。
この整合性を取る鍵となるのが、CFO・CIO・CSOによる共通KPI設計とデータ統合です。 つまり、シングルマテリアリティを軸にした法定開示と、ダブルマテリアリティを踏まえた価値創造ストーリーを接続する組織デザインが、今後の競争力を左右します。
ダブルマテリアリティからシングルマテリアリティへ─実務的な整理と統合のステップ
多くの日本企業はすでに、統合報告書などでダブルマテリアリティを起点にマテリアリティ特定を行っています。しかしながら、SSBJ基準への対応に向けては、既存のダブルマテリアリティ分析を基礎に、シングルマテリアリティの観点で再整理することが求められます。
そのための実務的なアプローチは次の3段階です。
- 財務影響軸へのマッピング
既存のマテリアリティ項目(例:気候変動・人権・サプライチェーン)を、企業価値への影響度で分類。財務的リスク・機会に関連づけて再定義する。 - 定量化のプロセス設計
CSO部門が把握している社会・環境データを、CFO・CIOが財務モデルと統合。KPIをROICやコスト指標に変換し、投資判断やリスク管理に連携させる。 - 開示体系の二層構造化
法定開示(SSBJ対応)はシングルマテリアリティを軸に、統合報告書など任意開示ではダブルマテリアリティを反映する二層構造を採用。これにより、制度要求とステークホルダー要求を両立できる。
このように、ダブルマテリアリティの広範な分析を基礎としつつ、SSBJが求める財務的視点へ落とし込む形で再構築することで、整合性と実効性を両立できます。結果として、社会価値と企業価値の双方を可視化する「二段階統合型マテリアリティ評価」が確立されます。
まとめ
シングルマテリアリティは「企業価値のための重要性」を、ダブルマテリアリティは「社会と企業の相互影響の重要性」を捉える考え方です。
SSBJ基準によって、企業はまずシングルマテリアリティで財務的影響を整理する必要がありますが、同時にダブルマテリアリティを通じて社会価値を表現することが、統合報告や国際的な信頼の獲得につながります。
CxO連携によるマテリアリティ評価の統合こそが、サステナ経営を「理念」から「実装」へと進化させる次のステップです。
出典
サステナ経営を実践する組織デザイン:CFO・CIO・CSOが連携して実現する価値創造モデル
サステナビリティ基準委員会(SSBJ)「サステナビリティ開示基準」
https://www.ssb-j.jp/jp/ssbj_standards.html
GRI(Global Reporting Initiative)「GRI Standards」
https://www.globalreporting.org