サステナビリティ第三者保証 ~SSBJ・金融庁が示す法令化の方向性~

目次
前記事では、サステナビリティ情報に対する第三者保証の実務上の課題として、情報整備、専門性の不足、コスト負担の3点を取り上げました。では、そもそもこうした保証はなぜ必要とされ、今後どのように制度として位置づけられていくのでしょうか。本記事では、サステナビリティ保証の制度的背景を俯瞰し、日本の基準策定機関であるSSBJ(サステナビリティ基準委員会)と金融庁による制度設計の動向をもとに、法令化の方向性を解説します。
第三者保証を導入する企業が増え続けている背景
サステナビリティ情報(GHG排出量、人的資本、気候関連財務情報など)とは、企業のサステナビリティ活動に関する情報であり、企業の中長期の価値創造を示す非財務情報です。近年、これらの情報に対し第三者保証を実施する企業は増加傾向にあり、G250企業(2023年度世界の売上高ランキング上位250社)の69%、日本企業は89%に上るとの報告もあります「出典①」。
この背景には、サステナビリティウォッシュを防ぎたい投資家・社会の目線と、企業が信頼性ある情報を届けたいという要請の一致があります。保証を受けることは単に形式的な“お墨付き”にとどまらず、企業の誠実性や説明責任を担保する経営インフラ、サステナビリティ経営の信頼性を担保する要素となりつつあります。
SSBJと金融庁が並行して進める制度化の全体像
日本におけるサステナビリティ情報の制度化は、SSBJによる基準策定と金融庁による制度設計・保証要件が並行かつ連携して進んでいます。
- SSBJは、ISSBのIFRS S1/S2基準と整合性のある日本独自の3つの開示基準を策定しており、有価証券報告書など法定開示文書への統合も視野に入れた基準となっています「出典②」。
- 金融庁は保証の制度導入を段階的に進める方針を明示しており、初期段階では限定的保証(Limited Assurance)が現実的とされる一方、将来的には合理的保証(Reasonable Assurance)を目指すという長期的な方向性が示されています「出典③」。
このように、現実的な導入負荷を踏まえたうえでの段階的制度化が想定されており、以下のような枠組みが進行中です:
- 保証の段階的導入:限定的保証から合理的保証へ
- 対象範囲の明確化:初期はGHG排出量(Scope1・2)や気候関連リスクなどから適用
- 柔軟な適用措置:中小企業には経過措置や簡便な選択肢を用意
- 保証の法定文書化:将来的に有価証券報告書等に保証付き情報として組み込まれる構想
このように、制度整備は、SSBJの基準策定と金融庁の制度設計という二つの役割が連携する構造で進められています。
保証の本質的価値と企業に求められる視座
保証の制度化は、企業にとって単なる規制対応ではなく、ガバナンスの高度化、社会的信頼の獲得、持続的価値の証明という戦略的意義を持ちます。制度対応の最低限を追うのではなく、保証取得を通じて情報の精度や統制体制を鍛えることが、結果的にESGの競争力強化にもつながります。
SSBJと金融庁が描く構想では、保証は「数値の正確性」だけでなく、「説明責任の履行」「内部統制の成熟度」「意思決定の透明性」など、経営そのものの信頼性指標として位置づけられます。
今後、保証制度が法制化された際に問われるのは、「保証をどう取るか」だけではなく、「どれだけ自社の意思決定と連動して保証可能な情報を持っているか」という企業体質です。
まとめ
サステナビリティ情報の第三者保証は、企業の任意の選択肢から制度的な要請へと変化しています。日本においては、SSBJが開示基準の策定を、金融庁が制度・保証要件の設計を担いながら、段階的かつ確実に制度化を推進しています。
特に金融庁は、限定的保証を制度の入口としつつも、将来的には合理的保証への移行を視野に入れており、企業はそれを見据えた長期的対応が不可欠です。制度対応にとどまらず、保証を通じて企業自身のガバナンス・戦略・人材を高める機会と捉え、持続可能な信頼構築の軸とすることが、これからのESG経営の本質といえるでしょう。
出典
- KPMGインターナショナル KPMGグローバルサステナビリティ報告調査2024
- SSBJ サステナビリティ開示基準
- 金融庁 「サステナビリティ情報の開示と保証に関するワーキング・グループ」(2024年5月14日)事務局資料
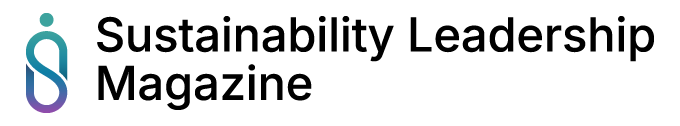


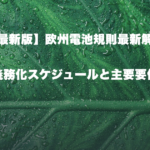
とは-―-製品のGHG見える化から企業全体の削減へ-150x150.png)
