SSBJ・CSRDに必須なサステナビリティ第三者保証 ~対応コストと導入格差の拡大にどう立ち向かうか~
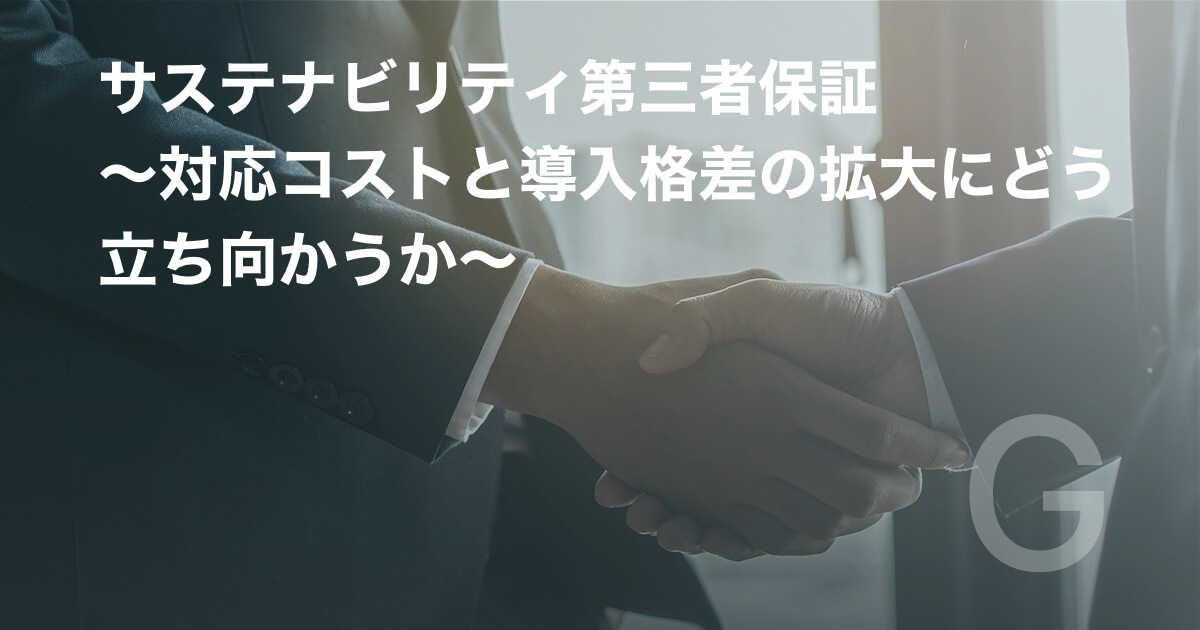
目次
サステナビリティ情報の第三者保証が制度として組み込まれ始めています。SSBJ(サステナビリティ基準委員会)による開示基準の策定、および金融庁の段階的な保証制度導入方針のもと、企業は任意対応から制度対応への転換を迫られています。さらに、経済産業省が主導する排出量取引制度においても第三者保証が必須となっています。
特に排出量取引制度では、初期段階では「限定的保証」から始めつつも、一定の期間経過後には「合理的保証」への移行が制度設計として明示されており、企業に求められる保証水準は今後ますます高まっていくと見られます。
こうした保証制度の拡大と深化に対して、企業はどのように備え、各企業がどのように対応していくべきか、本記事で考えてみます。
保証対象の拡大と企業への影響
第三者保証ではGHG排出量(スコープ1・2)に注目されていますが、金融庁は保証制度適用時期から2年間は、スコープ1・2に加えガバナンス並びにリスク管理に対する保証を義務付ける、3年目以降は、国際動向を踏まえ今後検討する、とあります。一方、同中間論点整理(案)には、「サステナビリティ情報の信頼性を確保するためには、その全てについて第三者保証が行われるべきという意見もある」との記述があることから、保証対象は拡大する圧力が絶えずかかり続けており、日本でも保証対象が拡大することが容易に想像できます。
加えて、経産省が設計する排出量取引制度では、排出量に関するクレジット制度を支える信頼性確保手段として、登録確認機関による「第三者確認=保証」が義務付けられるとされているとともに、以下のような「保証水準の段階的引き上げ」が明確に設計されています:
- 初期段階:限定的保証(Limited Assurance)
- 数年後の発展段階:合理的保証(Reasonable Assurance) (対象は大規模事業所などから段階的に適用)
つまり、制度設計そのものが「保証の制度化と高度化」を前提としており、今後のサステナビリティ保証対応は、形式的な導入ではなく継続的で構造的な体制整備が求められるフェーズに入っています。
データ収集と算定方法の比較
制度対応が段階的保証義務化へと向かうなかで、企業が採りうる実務対応の選択肢は、大きく次の2つに分かれます。
一つは、既存のExcelや手作業による集計・管理をベースに、外部コンサルタントの支援を受けるモデル。もう一つは、ERP等のシステムを用いて、サステナビリティ情報を構造化・標準化し、自社内で継続的に運用・保証に対応するモデルです。
以下は、両者の代表的な違いを示した比較表です。
| 項目 | アプローチ① エクセル+コンサル業務委託 | アプローチ② サステナビリティERP |
| 業務主導主体 | コンサル主導 | 自社内で一元管理 |
| 集計頻度 | 年1回(保証直前) | 月次・四半期で定期運用 |
| 集計費用 | 高(都度委託) | 中(初期投資+定常運用) |
| 保証費用 | 高(整合性が乏しく工数増) | 低(整備されたデータで効率化) |
| トータル費用 | 高 | 中長期で抑制可能 |
| 進捗管理 | 困難。定期レビューが不可 | 容易。PDCA型モニタリングが可能 |
| ガバナンス | 属人的・ブラックボックス化 | トレーサブルで監査対応も可 |
| 企業価値への貢献 | 限定的(制度消化となり、企業価値向上への活動につながりづらい) | 高(財務データとをリンクさせつつ、企業価値向上につなげるためには必要不可欠) |
このように、ERP型の導入は単に保証対応を効率化するだけでなく、組織的なガバナンスとESG戦略の高度化、企業価値向上を同時に実現するための基盤整備で必要な武器です。
ERPによる「集計頻度の高さ」がもたらす進捗管理とガバナンスの進化
ERP型の導入によって、単に集計を自動化するだけでなく、進捗管理・内部統制・保証対応が連動したガバナンス体制を構築できます。その結果、集計作業にとどまらず、企業価値向上につながる活動に連携できます。
- 進捗管理:財務情報同様、高頻度集計により、目標と実績の差分をタイムリーに把握
- 保証対応:一貫性のあるデータ構造と履歴管理により、保証人との確認が効率化
- ガバナンス強化:内部統制が仕組みとして組み込まれることで、企業全体の透明性が向上
- 企業価値向上:ESGスコア改善、財務情報との関連性向上、従業員・顧客・投資家からの信頼性向上に貢献
合理的保証への備えは急務
金融庁・SSBJの保証制度では合理的保証については現時点では否定的ではあるものの、経産省が設計する排出量取引制度では、保証水準が段階的に引き上げられ、限定的保証から合理的保証に移行していきます。すなわち、企業は限定的保証のみを対象としたガバナンス体制を構築・運営していくと、他制度への対応に遅れが生じてしまいます。国内制度(有価証証券報告書への報告と排出量取引制度)のみならず、海外の動向を理解し、将来を見据えた「保証対応の準備=制度開示の前提条件」となる時代が始まっています。
まとめ
サステナビリティ保証は、単なる制度対応ではありません。ERPを基盤にした自社完結型の運用モデルは、継続的な開示・保証・説明責任の連鎖を可能とし、GX制度やESG経営のあらゆる局面において「信頼される情報基盤」として機能します。
企業が今なすべきことは、保証対応の「やり方」を変えることではなく、「仕組みとして保証に対応する体制」に進化させることです。
出典
SSBJ開示基準 https://www.ssb-j.jp/jp/ssbj_standards/2025-0305.html
金融審議会「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」(第8回)資料1・2 https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/sustainability_disclose_wg/shiryou/20250627.html
経済産業省 GXグループ「排出量取引制度の詳細設計に向けた検討方針」 https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sangyo_gijutsu/emissions_trading/pdf/001_03_00.pdf
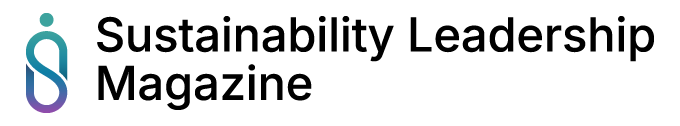


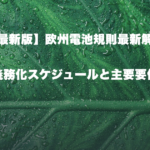
とは-―-製品のGHG見える化から企業全体の削減へ-150x150.png)
