SSBJ対応における第三者保証の位置づけと体制設計

目次
前記事(「SSBJ対応における第三者保証の前提となる内部統制と情報整備の考え方」)では、
第三者保証を検討する前提として、企業がまず確認すべき論点を整理しました。
中でも最も多くの企業が直面しているのが、「情報整備と内部統制の未成熟」です。保証制度が制度開示の中で本格化しつつある中、この課題にどのように取り組むべきかが、企業の対応力と信頼性を左右する分岐点となります。
本記事では、保証に耐えうる情報基盤を構築するために、企業が実践すべき対応策を3つの観点から解説します。
情報の保証対応力を高めるための前提整備
第三者保証に対応するには、データの「保証対応力」を確保することが第一歩となります。これは、データの正確性に加えて、出所の明確性・再現性・証憑との対応が担保されているかが問われるということです。
例えばGHG排出量を例に取ると、Scope1・2の算定に使用したエネルギー使用量や排出係数の根拠、ロジック文書、元データとの突合が可能な形で保管されていることが重要です。これらが事業部門ごとに形式や粒度が異なる状態であったり、情報をエクセルのバケツリレーで収集している状態では、保証を行う第三者機関が効率的に十分な評価をすることが困難となり、膨大な労力を要し、高コストとなるだけでなく、制度開示に間に合わないリスクが高まります。
なお、こうした前提が十分に整っていない状態で第三者保証の検討を進めた場合、想定以上の工数や調整が発生するだけでなく、保証人による十分な検証が難しくなるケースもあります。
サステナビリティ情報に対する保証では、「数値が合っているか」だけでなく、その算定プロセスや統制環境が適切に機能しているかまで評価対象となります。保証取得に先立ち、内部統制の見える化を図る文書整備や、ガバナンス・業務フローの明確化が不可欠です。
プロセスの標準化とデータ整備体制の構築
保証に向けた整備は単発のデータ整理で終わるものではなく、継続的に管理及び説明可能な体制を維持することが必要です。以下の3点が主要な整備項目です。
- 記録様式と定義の統一 拠点・部門を横断して整合性のあるデータ収集を実現するには、入力フォーマット、用語定義、単位などを全社共通化する必要があります。
- 定期レビュー体制の構築 データの収集頻度を明確にし、月次・四半期でのレビュー・差異分析・修正フローを設計することで、データの信頼性を高めることができます。
- エビデンス管理とトレーサビリティ 算定根拠や入力値の証憑・エビデンス、計算式のバージョン管理など、すべての情報が時系列で追跡可能な状態にしておくことが、保証機関とのコミュニケーションを円滑にし、効率的な第三者保証の実施につながります。
KPMGジャパンの『日本の企業報告に関する調査2023』でも、サステナビリティ報告の信頼性担保には、保証に耐えうる情報収集体制・内部統制・業務フローの整備が不可欠であることが強調されています。これらを解決するためには、情報の承認機能を多段階で設定可能な情報収集プラットフォームの利活用が効果的です。
内部統制との連携と保証対応型ガバナンス
前述の通り、サステナビリティ情報に対する保証は、数値の正確性はもとより、数値の入手から算定に至るプロセス全体が確認されます。つまり、保証対応には内部統制の観点が不可欠です。
企業が取り組むべき具体策は以下のとおりです:
- 責任分担の明確化 収集、チェック、承認といった各プロセスにおける役割と担当者を明示し、文書化する。
- 内部監査の活用 サステナビリティ情報にも財務監査と同様の内部監査の視点を導入し、客観的な確認プロセスを確立する。
- 保証機関との初期対話 保証を依頼する段階になって慌てるのではなく、事前に保証人と想定される組織と対話を行いつつ、保証に耐えうる統制のしくみを設計することが推奨されます。
なお、SSBJ対応における第三者保証の位置づけや水準は、他制度との違いも踏まえつつ整理しておく必要があります。
まとめ
サステナビリティ情報の第三者保証における「情報整備と内部統制」は、企業にとって避けては通れない重要なテーマです。保証対応を可能にするためには、①保証可能な情報伝達のしくみ化、②標準化と継続運用の仕組み、③統制・監査・対話を通じたガバナンスの強化が欠かせません。
さらに、これらを実務の現場で確実に機能させるためには、Excelによる属人的な集計には限界があることを直視する必要があります。サステナビリティ情報は、財務情報と同様に、整合性、改ざん防止、トレーサビリティを備えた管理基盤の上で初めて、保証に耐えうる品質を確保できます。
なお、第三者保証を検討する前提として、内部統制や情報整備をどのように捉えるべきかについては、以下の記事で整理しています。
一方で、保証対応を実際に進めていく段階では、コストや体制格差といった現実的な論点も避けて通れません。
これらについては、次の記事で詳しく解説しています。
出典
日本会計士協会 解説記事・国際監査・保証基準審議会(IAASB)国際サステナビリティ保証基準(ISSA)5000「サステナビリティ保証業務の一般的要求事項」 【解説記事】国際監査・保証基準審議会(IAASB)
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20250317dcx.html
KPMGジャパン『日本の企業報告に関する調査2023』
https://kpmg.com/jp/ja/home/insights/2023/09/sustainability-reporting-survey-2023.html
金融庁金融審議会「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」(第8回)資料1 https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/sustainability_disclose_wg/shiryou/20250627.html
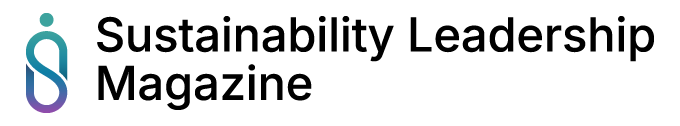
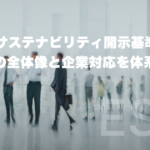

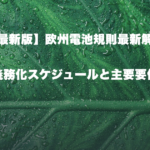
とは-―-製品のGHG見える化から企業全体の削減へ-150x150.png)
