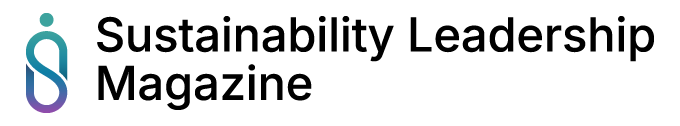【第2回】MSCI ESGレーティングを解説:Key Issue評価と企業が備えるべき視点
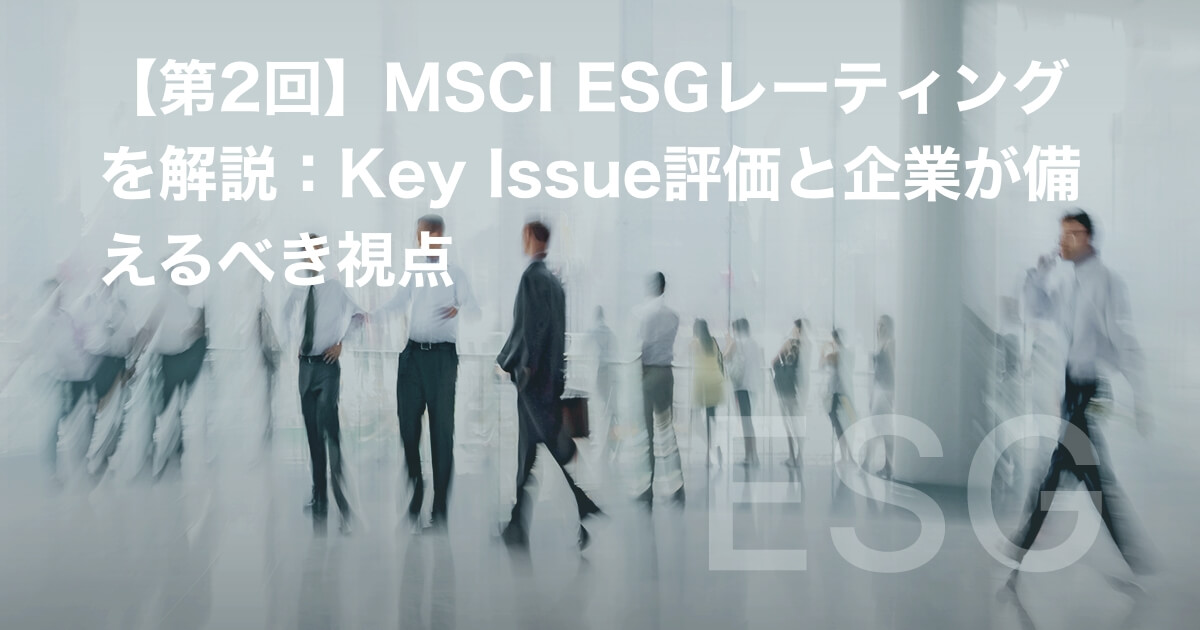
目次
MSCI ESGレーティングが投資判断の基盤として定着する中で、企業に求められるのは“評価される仕組み”を理解するだけではなく、自社のどこがどのように見られているかを把握し、実務的に経営レベルの向上をすすめていくことです。
本記事では、「重要課題(Key Issue)」の具体例として「生物多様性と土地利用」を取り上げながら、スコアの構造、実務上の視点、そして他評価機関との比較までを解説します。
Key Issue評価とは:ESG評価の中核
MSCIは、ESGに関連する業界特有のリスク・機会をKey Issueとして設定し、GICS(Global Industry Classification Standard)に基づく各業種に2~11項目を割り当てます。評価は「リスク曝露度(Exposure)」と「管理能力(Management)」のバランスに基づき、0~10点でスコア化されます。この仕組みにより、同一課題でも業種や地域による違いを考慮した評価が可能となっています。
Key Issueの全体像
MSCIは環境・社会・ガバナンスの3分野で計33のKey Issueを定め、業種ごとに重点課題を設定します。例えば、エネルギー業界では気候変動、IT業界ではデータプライバシーが重視されます。自社の業種に該当するKey Issueを把握することで、ESG戦略の優先項目を明確化できます。

Key Issue実例:生物多様性と土地利用の評価枠組み
ここでは、環境分野の一例として「生物多様性と土地利用(Biodiversity & Land Use)」を取り上げ、鉱業、農業製品、インフラ・公益事業など、自然資源利用と土地改変に密接に関わる業種を中心に、特に生物多様性の敏感な地域に事業資産を持つ企業について、MSCIがどのようにリスクと対応を評価しているのかを見てみましょう。
この指標の評価は、以下の2つの主要な軸から構成されています:
1. 曝露スコア(Exposure Score)
企業が生物多様性リスクにどれだけさらされているかを0~10点で評価します。構成要素は:
- ビジネス面の曝露(Business Exposure Score):事業セグメントの自然資源依存度や生物多様性への影響(例:森林伐採による訴訟頻度)を評価。
- 地理的曝露(Geographic Exposure Score):地域の森林減少面積や絶滅危惧種数に基づき、企業資産の地域分布を加味してスコア化。

図2:生物多様性曝露スコア
2. 管理スコア(Management Score)
企業がリスクにどう対応しているかを以下の3つの観点で評価(各0~10点):
- 方針と情報開示(Policies & Disclosure):
- 森林破壊ゼロなどの明確な方針の有無。
- サプライチェーンを含む情報開示の範囲。
- 第三者認証(例:RSPO)のカバー率。
- 実行体制(Programs & Structures):
- 生態系保護の取り組み(例:保護区整備)の包括性。
- 新規事業での生物多様性影響評価(BIA)の実施状況。
- 定量的パフォーマンス(Performance):
- 石油流出強度(例:油流出量/売上)や水使用量などのデータ。
- 業界平均との比較や改善トレンド。
これらの平均が「管理スコア(Controversies除外)」となり、重大インシデント(例:環境破壊による訴訟)があれば0~5点の減点が加わる「論争スコア(Controversies)」を反映し、最終管理スコアが決定されます。なお、管理スコアと論争スコアを組み合わせる評価手法は、生物多様性と土地利用に限らず、MSCI ESGレーティング全体で共通して用いられています。
実務で備えるべき視点
「生物多様性と土地利用」を例に、MSCIの評価基準に対応する実務的準備を以下にまとめます。他のKey Issue(例:気候変動、労働条件など)についても、同様にKPIを分析し、改善策を検討するという視点でアプローチすることが可能です。
- 方針の明確化:森林破壊ゼロなどの方針を策定し、サプライチェーンまで適用。
- KPIの整備:水使用量や土地回復率などの指標を整備し、改善実績を開示。
- 外部認証:RSPOなどの認証を取得し、NGOと連携して信頼性を強化。
- 論争予防:環境影響評価(EIA)や住民対話で紛争を早期解決。
MSCIの評価構造に対応した取組を進めることは、TNFDなどの国際的枠組みとも整合性を取りやすく、持続可能な経営の基盤強化につながります。
まとめ
MSCI ESGレーティングにおける「Key Issue」は、単なる評価項目ではなく、企業ごとのリスクと機会を可視化するレンズであり、持続可能な経営の優先領域を明らかにする出発点です。
自社に割り当てられたKey Issueを深く理解し、その構造的な評価軸に対応した取り組みを進めることで、ESG対応は「開示の義務」から「経営の選択肢」へと進化していきます。
出典
- MSCI ESG Ratings Methodology(日本語)
- MSCI Nature and Biodiversity Solutions :MSCIがTNFDやCSRDに整合する自然資本分析フレームを提供していることを明記
- Sustainable Japan MSCIとNatureAlpha、TNFD対応の自然資本指標を共同提供:MSCIが生物多様性リスク対応で外部パートナーと提携した事例を紹介
- 年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)ESG投資に関する取組