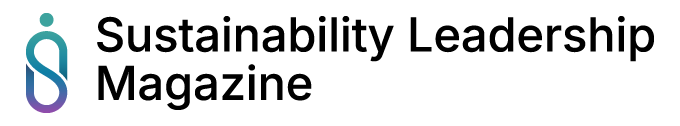【第2回】FTSE RussellのESGモデルを解説:評価プロセスと改善アプローチ

目次
前回の記事では、FTSE RussellのESGレーティングモデルの構造と国際的な整合性について紹介しました。本記事は、具体的な評価プロセスと、企業がESGスコアを向上させるための戦略について掘り下げていきます。
評価プロセスの詳細
FTSE RussellのESGレーティングモデルは、年間を通じて実施される調査と透明性のあるプロセスに基づき、企業のESGリスクおよび対応状況を定量的に評価します。この評価結果は、持続可能性に優れた企業を選定するESGインデックス(例:[FTSE Blossom Japan Index](https://www.lseg.com/en/ftse-russell/indices/blossom-japan?_gl=1*mof44b*_gcl_au*ODg5ODA3ODQzLjE3NTE1MDQ4OTM.))の構成銘柄選定に活用されます。以下の図は、調査からインデックス選定までの流れを示しています。

1. 企業情報の特定と分類(4月〜翌年2月)
まず、FTSE Russellは調査対象企業の事業構造、活動国、収益構造などの基本情報を収集します。このプロセスでは、企業の業種や特性に応じたESGテーマとリスクレベルの選定が行われ、評価の基礎が構築されます。
この初期プロセスにおいては、企業情報の分類と識別における一貫性と客観性を確保するために、以下の標準コード体系や分類基準が用いられています:
- [ICB(Industry Classification Benchmark)](https://www.lseg.com/ja/ftse-russell/industry-classification-benchmark-icb?): FTSE Russell独自の業種分類システムであり、企業をセクターや業種レベルで分類します。これにより、例えば製造業では「気候変動」、金融業では「ガバナンス」など、業種特有のESGリスクを適切に評価できます。
- SEDOL(Stock Exchange Daily Official List): SEDOLコードは、企業の株式・証券ごとに付与される識別子で、FTSE Russellのデータベース上で企業を一貫して管理・トラッキングするために使用されます。調査・評価・インデックス組入れの各ステップでこの識別情報が活用されます。
2. 初期評価とレビュー(5月〜翌年3月)
続いて、FTSE Russellは、企業に該当すると判断されたESGテーマについて、公開情報に基づき初期評価を行います。評価では、各テーマにおける情報開示の有無や充実度などが中心となり、定量的にスコア化されます。
- 初期評価結果は企業に送付され、企業は内容に対してフィードバックを提出することが可能です。
- 提出された意見を踏まえ、FTSE Russellは必要に応じて追加調査を行います。
- 評価の修正は原則として公開情報に基づくものであり、未公開の内部資料は評価対象になりません。
3. スコアの最終決定と公開(6月末・12月末)
- 企業からのフィードバックおよび追加調査結果をもとに、テーマごとのスコアが算出され、それを統合して環境・社会・ガバナンスの各カテゴリ、および総合ESGスコアが導き出されます。
- 年2回、6月末と12月末に最終スコアが公開されます。
4. インデックス構成銘柄の決定
- 公開されたESGスコアを基に、[FTSE Blossom Japan Index](https://www.lseg.com/en/ftse-russell/indices/blossom-japan?_gl=1*mof44b*_gcl_au*ODg5ODA3ODQzLjE3NTE1MDQ4OTM.)や[FTSE Blossom Japan Sector Relative Index](https://www.lseg.com/en/ftse-russell/indices/blossom-japan?_gl=1*mof44b*_gcl_au*ODg5ODA3ODQzLjE3NTE1MDQ4OTM.)、FTSE4Good Index SeriesなどのESGインデックスへの組入れが決定されます。
- 組入れは、一定スコア基準を満たすかどうかにより判断され、ESG投資対象としての信頼性を企業に付与します。
このように、FTSE RussellのESGレーティングモデルは、厳格で透明性のあるプロセスを通じて企業の持続可能性を評価し、信頼性の高い情報を提供しています。この評価を活用することで、企業はESGスコアを戦略的に向上させ、投資家やステークホルダーとの信頼関係を強化することが可能になります。
次に、ESGスコアの向上がもたらす具体的なメリットについて見ていきましょう。
ESGスコア向上のメリット
FTSE RussellのESGスコアは、パッシブ運用に採用される複数のESGインデックスにおいて、構成銘柄の選定基準として活用されています。特に、年金運営機関や機関投資家が採用する代表的な指数では、一定以上のESGスコアを満たすことが重要な条件とされています。
スコアを向上させることで、企業は以下のような具体的メリットを享受できます:
- 投資家からの信頼性向上:ESG評価の高い企業として認知され、株式市場における信頼が高まります。
- 資金調達の円滑化:ESG投資の拡大により、スコアが高い企業は投資先として選ばれやすくなり、資金調達が有利になります。
- 企業価値の向上:持続可能性に配慮した経営が評価され、長期的な企業価値向上につながります。
特に、世界最大級の運用資産を持つGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)は、2017年度からESG指数を用いたパッシブ運用を開始しており、その中にはFTSEのESGインデックスも含まれています。GPIFは、企業の非財務情報に基づいて構成銘柄が選定されるESG指数を9つ選定しており、2023年度末時点では、それらに連動する運用資産額は約17.8兆円に達しています。これは、ESG投資が長期的なリターンの向上に寄与し得るという考えを裏付けるものです。

図2:GPIFが採用するESG指数一覧 (出典:GPIF)
ESGスコア向上のための戦略
企業がFTSE RussellのESGスコアを向上させるためには、以下のステップが有効です:
1.重要ESGテーマの特定
自社の事業構造や業種特性を踏まえ、評価対象となるESGテーマを整理します。どの分野においてESGリスクや機会が大きいのかを可視化することが第一歩です。
2.ギャップ分析と課題の優先順位付け
現在の情報開示内容を分析し、FTSE Russellの評価項目とのギャップを洗い出します。開示不足や改善余地のある領域を特定し、対応すべき課題に優先順位を付けます。
3.具体的な改善アクションと開示支援
開示の強化に向けたアクションを設計し、必要なデータを補完します。他社事例や国際的な開示フレームワーク(例:CDP、TCFDなど)を参考に、具体的な情報開示の質と量を高めることが有効です。
まとめ
FTSE RussellのESGレーティングモデルは、厳格な評価プロセスと戦略的な情報開示を通じて、企業の持続可能性を高め、FTSE Blossom Japan IndexをはじめとしたESGインデックスへの組み入れを可能にします。積極的なESG取り組みにより、GPIFのような投資家の信頼を獲得し、グローバルな競争力を強化できます。ESGスコアは、単なる評価ではなく、企業の中長期的な競争力を示す「非財務のパスポート」です。今後もスコア向上を戦略的に進めることが、企業価値の持続的成長に直結します。
出典
年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)ESG投資について
JPX × FTSE Russell FTSE ESGレーティングとインデックスについて
ロンドン証券取引所グループ(LSEG) FTSE Russell ESGスコア
FTSE Russell FTSE Russell ESG Ratings Data Model: Methodology
ロンドン証券取引所グループ(LSEG)Industry Classification Benchmark (ICB)